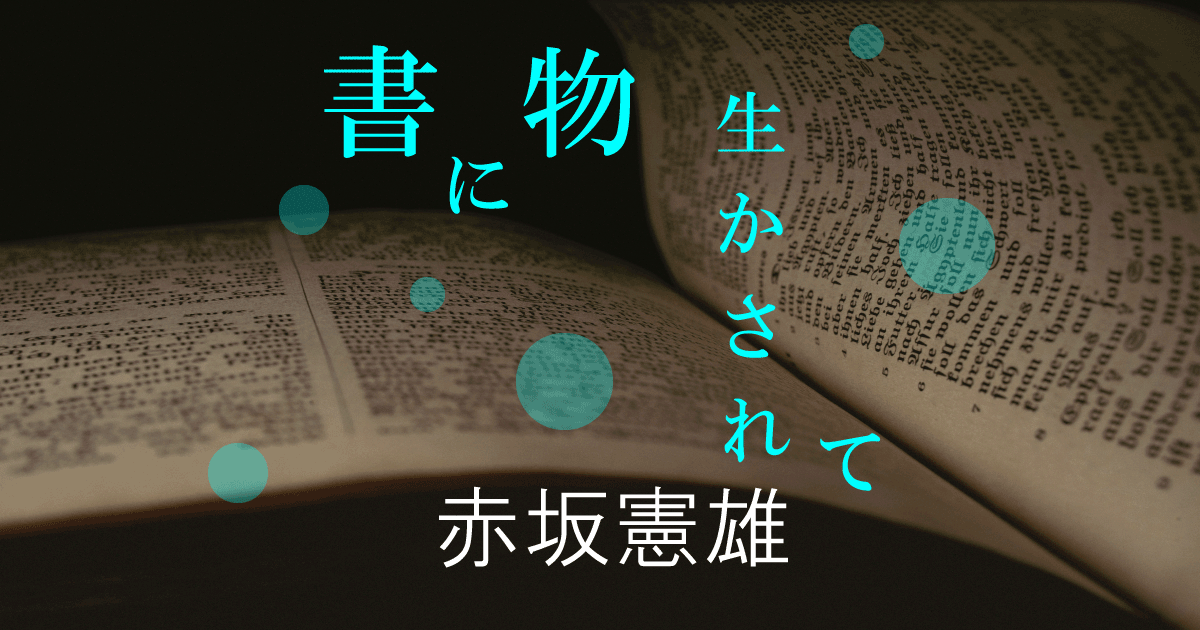はじめて読んだ本は覚えていない。家には子どもが読めるような本はなかった。絵本などというおしゃれなものは、むろんなかった。日本社会はいまだ、高度経済成長期の手前にいて貧しかった。わが家はさらに貧しかった。
小学校には、古びた教室を改装しただけの図書室があった。低学年のころは、決まって土曜日に、本を借りて帰った。その午後は至福の時間だった。薄暗くなるまで、夢中で読みふけったが、なにを読んだのかは、意外なほどに覚えていない。野口英世やエジソンなどの偉人のシリーズ、『トム・ソーヤの冒険』などが、ぼんやりと浮かぶだけだ。テンボウの母が木蔭に隠れて、教室を覗いている。そんな挿し絵が妙に鮮明に残っている。
はじめて買ってもらった本のことは、すこしだけ記憶している。お年玉を貯めて買った。府中の北のはずれに住んでいた。本屋さんは歩いて三、四十分ほどの府中の街場にしかなかった。母といっしょであったが、自分で選んで買った。これでいいのね、と念を押された。貧しい家の、十歳の少年には、とても贅沢な買い物だったかと思う。表紙が茶色っぽかった印象がある。なぜか、400円という数字が頭に浮かぶ。六十年足らず昔のその本は引っ越しをくりかえすうちに、いつしか姿が見えなくなった。
書名はたぶん、『ロビンソン漂流記』であった。思い立って、ネットの「日本の古本屋」で探してみた。再会はたやすかった。検索に引っかかった四冊の本を注文すると、日をおかずに届く。眺めるとすぐに、これだとわかった。講談社の少年少女世界文学全集の一冊、『ロビンソン漂流記 シェークスピア物語』であった。値段は380円とある。わたしはきっと、百円玉四枚を握りしめて、この、装丁などもなかなか立派な本を買ったのだ。これでいいのね、うん。十歳の少年のはじめての買い物は本だったことになる。ただし、後半にシェークスピア物語がくっついていたことには、驚かされた。かけらも記憶にはなかったのだ。ただ、頭のどこか片隅には、「ベニスの商人」を読んだ記憶はあって、おそらくこの茶色い本の後半も読むだけは読んでいたにちがいない。
奥付けには、昭和三十四年三月二十日の発行と見える。訳者は中野好夫であった。もしかすると、わたしはもうすこし幼かったのかもしれない。挿し絵が少なくて、背伸びした記憶が残っているのである。なかなか読み終わらなかった。もったいなくて速読みができなかったのか、むずかしかったのか、いまとなってはわからない。
それでも、わたしのなかでは、無人島や探検といったテーマが大流行になった。寝ても覚めても探検ごっこの日々であった。武蔵野の壊れてゆく風景のなか、かろうじて開発から逃れていた雑木林や原っぱが遊びの舞台になった。草や藪を掻き分けて、あやしい人や物を探しまわった。いつだって、ヒロシ君といっしょだった。むろん、上下関係などはなかったが、かれが相棒のフライデーということになる。すり傷にはすかさず携帯用にしつらえた赤チンを塗り、道々、ビスケットをかじって飢えをしのいだ。夜は夜で、寝つきがわるくて、ロビンソン・クルーソーやトム・ソーヤの跡を追いかけて、つかの間のさすらいの旅に出た。
十歳のすこし手前にいたわたしはたしかに、谷川雁のいう、木や小川や動物も戯れる相手にしてしまう、男の子にとっての「幻想性の時代」、「人生の二番目の黄金期」(『意識の海のものがたりへ』日本エディタースクール出版部、1983)を生きていたのだった。はじめて自分のものになった茶色い本との出会いをきっかけにして、探検や無人島に憧れる日々が幕を開けたことだけは、あきらかだった。
そのはじまりの章は「家出」と題されていた。すぐに、こんな一文にぶつかる、「わたしは三男で、……小さいときから、ぼんやりと旅に出ることばかり考えてくらしていた」と。わたしは五男で、末っ子だった。夜ごと空想の旅には出たが、ほんとのところ旅という言葉を知っていたのかすら、あやしい。夢見がちではあったが、どこにでもいる平凡な少年にすぎなかった。
幼いわたしは、無人島に漂着した男の物語を読んだ、いや、やはり食べたのだと思う。わたしのからだはたしかに、その物語を記憶している。からだのどこかに痕跡が残っている。とはいえ、言葉の記憶ではない。思いがけず、色刷りの挿し絵であった。ロビンソン・クルーソーが浜辺に流れ着いた場面や、フライデーとの出会いの場面などは、あくまで映像的でありながら、モノクロームの記憶である。
それにしても、わたしはなぜ、『ロビンソン漂流記』を選んだのか。実をいえば、まったく覚えていない。一冊の本を手に取り、選ぶことには、なにか謎めいたものが潜んでいるのかもしれない。机の隅に立てかけられた茶色い本を、あらためて読んでみたくなる。この連載は記憶の海に沈んでいる本たちとの、再会の物語になりそうな予感がある。そんなことを考えながら、わたしがふと手に取ったのは、『完訳 ロビンソン・クルーソー』(中公文庫、2010)であった。完訳という言葉にそそられたのかもしれない。増田義郎の訳であり、かなり長編の解説が付いていた。この人はむろん、ラテンアメリカ文化史の研究者として著名な方であり、若いころに『インカ帝国探検記――ある文化の滅亡の歴史』(中央公論社、1962)などを読んだことがあった。
さて、増田義郎訳の『ロビンソン・クルーソー』との出会いは、ほとんど衝撃的なものであった。それはたぶん、子ども向けの『ロビンソン漂流記』を読んで以来、半世紀あまりが過ぎてからの再読であった。一冊の書物が人それぞれの人生のなかで、読むごとに読後感が変わり、いくつもの貌を見せることは珍しいことではない。だれかの示唆によって、まるで異なった読み方を教えられることもある。わたし自身が奴隷や家畜といったテーマに深く関心を寄せていた時期に、再会できたことは幸いであった。絶海の孤島に漂着したロビンソン・クルーソーが創意工夫を凝らして、二十八年の歳月を生き抜いた物語というイメージは、みごとにひっくり返った。
五、六年前であったか、カイル・オンストットの『マンディンゴ』(河出書房新社、1968)という、アメリカの「黒人奴隷の飼育を専門にしている農場」(安部公房「内なる辺境」)を舞台とした小説と、ほんの偶然に出会った。それを読み解くために、若いころに読んだ、山下正男の『動物と西欧思想』(中公新書、1974)を読みかえすことになった。その「結び」の章に、「アメリカでは、ヨーロッパ人種が動物について長年蓄積してきた技術のすべてがそっくり黒人奴隷に適用された」という言葉を見つけた。それがわたしを、遠く忘却の淵に沈めてきた『ロビンソン漂流記』のかたわらに導いてくれた。フライデーという奴隷をめぐる一節を読んだときの、なにか異物感が、痕跡のようなものとして身体のどこかに刻まれていたのだった。
わたしはいま、少年少女世界文学全集版にはさまれた色刷りの挿し絵を眺めている。赤いヒモ状の褌のほかはなにも身につけていない、素裸の「蛮人」が、毛皮の帽子や衣服や靴をまとって立つロビンソン・クルーソーの前にひざまずき、その足を押しいただいている。のちにフライデーと名づけられる黒い若者が、助けてくれたことを感謝し、奴隷として仕えることを身振りで申し出ている場面であった。背後の海辺には、ロビンソン・クルーソーが銃で殺した裸の男が転がっている。その男たちはフライデーを殺して喰らおうとしていたのだ。思えば、そこには主人と奴隷、白人と黒人、文化と野蛮、衣服と裸体、西欧と植民地といった、まさしく西洋中心主義の二元論的な構図がむきだしに描かれていた。むろん、幼いわたしがそんなことに気づいたはずはない。しかし、神のように立ち尽くすロビンソン・クルーソーが、左手に銃をたずさえ、右手を広げてフライデーの頭に翳している姿は、この物語の核心を示唆していたにちがいない。幼いわたしはきっと、わけもわからず畏怖を覚えたのではなかったか。
中公文庫版に付された増田義郎による、「大西洋世界のロビンソン・クルーソー」という長い解説は、かぎりなく刺激的なものであった。増田がキーワードにしたのは奴隷や奴隷貿易といった言葉である。ロビンソン・クルーソーが故郷のイギリスから、西アフリカを経由してカリブ海の無人島にたどり着くまでの軌跡そのものが、奴隷貿易というテーマによって支えられている。十八世紀以降、イギリスのマニファクチュア製品を満載した貿易船は、西アフリカでそれを黒人奴隷に換えて奴隷船となり、大西洋を横断して、カリブ海地域で売却し、砂糖などの産物を購入してイギリスへと帰還したのだった。こうした三角貿易で獲得された巨大な富が蓄積され、のちに西欧の産業革命へと道を開いた、そう、増田は述べている。そして、『ロビンソン・クルーソー』という物語は、この三角貿易の構図をなぞるように展開していた。ロビンソン・クルーソーはまさに、無人島の内/外を繋ぎながら、奴隷売買と植民地をめぐって、大西洋を舞台に活躍した初期資本主義の冒険的な担い手として造形されていたのである。
あらためて、増田訳の『完訳 ロビンソン・クルーソー』を読んでいると、家畜と奴隷のテーマが周到に描き込まれていることに気づかされた。いかにして、野生を飼い馴らし、とりわけ島の野生動物たちを家畜化するか。そうした野生と文化を繋ぐための試行錯誤が、やがて黒人の若者の登場とともに、奴隷の誕生をめぐる物語への伏線をなしていた。もはや、これを一人の男が無人島に漂着して、二十八年間を生き延びた壮絶な冒険譚として読み流すわけにはいかない。十九世紀に北アメリカで固有の展開を遂げた奴隷制度のなかに、家畜と奴隷のテーマが底流していたことが、ここから再考されねばならない。資本主義とは、現代にいたるまで家畜と奴隷をめぐる制度によってこそ支えられていることを、記憶に留めておきたい。
幼き日に読んだロビンソン・クルーソーの物語が、わたし自身の血肉と化して、いまに残っていたことに、不思議な感慨を覚えている。この連載はそんな気づきとともに、おずおずと幕をあける。