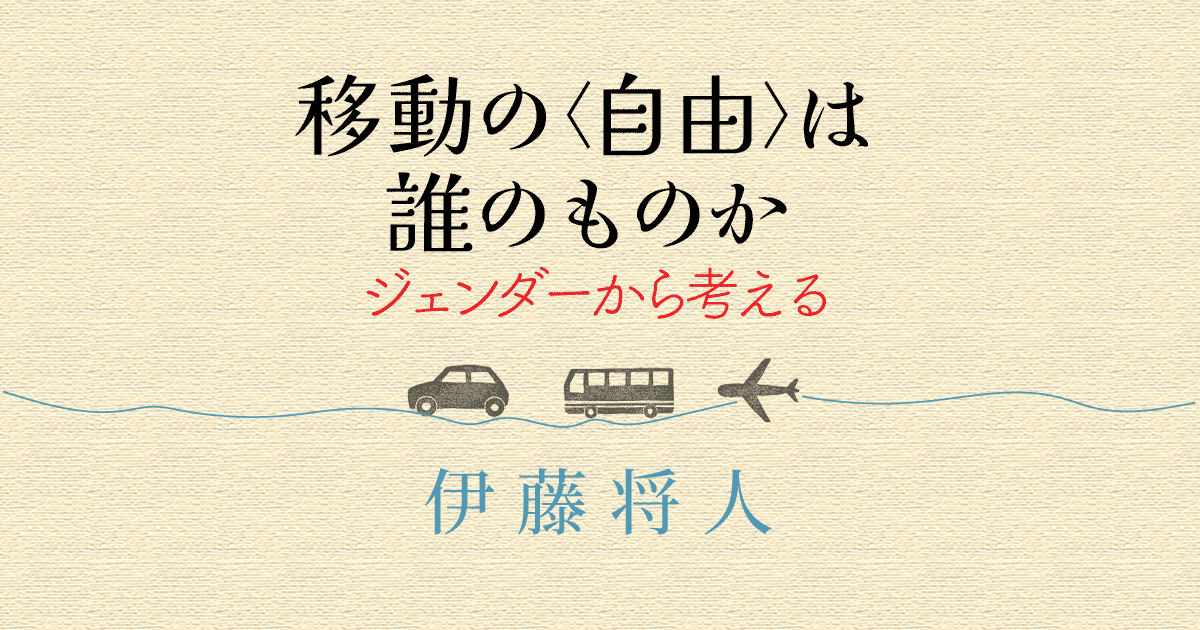7月末は、亡くなった父の誕生日なんですよね。だから、毎年この時期になると、あの世の父のもとに行きたくなるんです。今回こそは私もと思ってしっかり準備したつもりだったんですが、どうしてか、うまくいかなくて。だからこうして、いま話しているんだけどね。[1]
自分の身体を思いどおりに操れないもどかしさは、ときに生きる意味そのものを失わせる。
自由に移動できる環境が、自分にはない。
やりたいことは山ほどあるのに、何もできない。
そうして、また一日が過ぎていく。
30歳になる羊子さん(仮名)は、発達障害と精神疾患を抱えながら生きている。思うように働けないため、数年前から生活保護を受給している。彼女は筆者にとって、調査協力者であり、古くからの知人でもある。
鬱病で思うようにならない身体、その日になってみないとわからない心の安定性、支えでありながら制約でもある支援制度――生活保護は、引っ越しや自動車の所有といった移動をめぐる機会を大きく狭める[2]。そうした諸条件が重なり合う羊子さんの経験を通して見つめると、移動は簡単なことではないと気づかされる。だが同時に、ままならない状況の中でも、移動する術を探り当てることがあるのも確かだ。
今回は、羊子さんという一人の女性の語りと実践を糸口に、移動性(mobility)/非移動性(immobility)にひそむ自由と不自由を考えてみたい。キーワードは、「主体的な移動」と「仮想現実空間の移動」である。
「主体的な移動こそ素晴らしい」という幻想
昨今、「移動が成功をもたらす」という言説が巷で支持を得ている。移動とビジネスや人生における成功を結びつけた本がベストセラーになり、自らを成功者と位置づける人びとが、移動の重要性を声高に説く。
複雑性や予測不可能性、自己責任論が強まる現代社会において、「主体性」は最もわかりやすい美徳として、そうあるべきという規範として、人々の内面に刷り込まれていく。次期改訂の『学習指導要領』にむけた論点整理にも、「『主体的・対話的で深い学び』の実装」という文言が載っている。子どもの頃から「主体的であれ」と教えられる。自分の意思と判断で行動し、その結果に責任を引き受ける態度こそが望ましい、と。
では、なぜ、主体的であることが称揚されるのか。理由はいくつもあるが、主体性が「自分の意思で行動すること」と強く結びついている点は大きい。行動するとは、すなわち移動することだ。「いますぐ会いに行け」「百聞は一見にしかず」、こうした言葉たちが、主体性の証明として、移動することを日常的に求めてくる。
つまり移動は、主体性の最も手近で重要な発露として位置づけられる。だから「成功したいなら移動せよ」と言われる。挑戦とは“一歩を踏み出すこと”だ、と。裏返せば、その“最も簡単”に見える一歩すら踏み出せない者は主体性がない、ゆえに成功できない、だから移動せよ――という論理になる。
しかし、この思考(他者への主体的な移動の要求)――もはや、イデオロギーと呼んでもいい――には決定的な欠陥がある。それは、この世界に数多いる「移動したくてもできない」他者への想像力の欠如だ。移動力を振りかざす思想は、好きなときに好きな場所に移動できる極めて限られた特権的な移動強者中心の思想なのである。
この事実を改めて思い知らされたのは、羊子さんの何気ない一言だった。
鬱のときって、本当に何もできないんですよね。ベッドに縛り付けられている感じというか、文字どおり何もできない。どこか外へ出かけるなんて考えられない日が、何日も続くことがよくあるんです。
移動強者は、自分の移動を「能力や努力、実績の当然の帰結」とみなし、移動性の低い人びとを見下す言動を取ることがある(マッチョなビジネス系コンテンツに顕著だと感じるのは筆者の偏見だろうか)。「できないなんて言わず、今すぐ動けばいい」「海外へ出る勇気がないから成功しない」「なぜ、その場を離れられないのか」、移動勝者の側からは、そんな声が聞こえてくる。そして、移動したいけれどできなかった人、移動しようという考えさえ浮かばない状況に置かれた人は、その言葉を内面化し、「移動できない責任は自分にある」と、より強く自分を責めがちになるのである。
VRと移動
では、羊子さんは遠方への移動や思いどおりの移動ができないから、主体性を発揮していないというのだろうか。全く移動していないのかというと、そんなことはない。むしろ最近は、「移動」を楽しんでいるという。行く先は「仮想空間(メタバース)」である。「VR(仮想現実)」によって、彼女は移動するのだ。VRは、思うように移動できないもどかしさややるせなさを抱える人に、一筋の光をもたらす。
たとえば、現実世界では困難な旅行も、VRなら可能になる。
「空が広いよ」
「近くを女性が歩いている」
2023年1月、東京大学の研究者は広島県呉市の特別養護老人ホーム「仁方」で疑似旅行の体験会を実施した。戸惑いながらVRゴーグルを装着した特別養護老人ホーム利用者は、目の前に広がるハワイの風景を追う。映像は、まるでその場に立っているかのようで、体験後には「足もとにきれいな砂浜が広がっていて、実際に旅行した気分」と笑顔がこぼれた(田野口, 2023)。これまで高齢になると難しかった「旅行」が、仮想現実によって生涯の終わり近くまで可能になるかもしれない。
ジェンダースイッチングによる解放
物理的な空間で身体を動かすことが難しくても、仮想空間に入れば、言うことを聞かない自分の身体からふっと解放される。そして同時に、現実世界にまとわりつく「女性だから」「男性だから」というジェンダー規範からも一時的に離れることができる。そこに居心地のよさがある、と羊子さんは語る。
バーチャル美少女ねむと人類学者のリュドミラ・ブレディキナによる大規模調査「ソーシャルVRライフスタイル調査2023」によれば、仮想空間では男性ユーザーの75%が女性型アバターを利用(ジェンダースイッチング)している。現実世界において男らしい振る舞いを求められることにストレスを感じる男性ユーザーが、女性アバターを選択する傾向を示した研究もある(林,2024)。
さらに言えば、選ばれるアバターは人間に限られない。人間アバターを利用するユーザーは全体の41%に留まり、亜人間(semi-humanoid)を利用する人が47%、残りの12%は人間ロボットやサイボーグ、動物、植物、モンスターといったアバターを利用している。つまり、メタバースは「人間であること」「ある性別であること」からの一時的な離脱を可能にしているのである。
小型化されたモビリティーズが拡張する移動可能性
仮想空間は、移動の常識も一変させる可能性を秘めている。現に羊子さんも、現実の物理世界では移動をめぐる困難を多々感じるが、仮想空間ではどこまでも、何時間でも移動し、さまざまな人と出会い、話し、交流している。
仮想空間では、女性であることや障害を抱える現実から距離をとれる。「できるなら、体を取っ払って“水槽の脳”になりたい」と冗談めかして言う羊子さんにとって、VRは他者とコミュニケーションする手段であると同時に、自由な移動を実現する技術でもある。
社会学者アンソニー・エリオットとジョン・アーリは、「小型化されたモビリティーズ」が、高まる「移動しながらの生活」を加速させていると指摘する(Elliot and Urry, 2010=2016)。移動的な生活(モバイル・ライフ)の只中で、デジタル技術が、いかにして人間と物質世界に編み込まれていくのか、この問いに応える概念である。小型化と洗練を重ねるデバイスによって、身体と折り合う技術と使用者の操作能力も急速に発達してきた。都市社会学者マニュエル・カステルの言葉は、そうした世界と自己の変容をよく捉えている。
私たちの世界を特徴づけるものは、相互作用のネットワークにおける、人間の主要な部分である体と心の拡張と増大である。この相互作用は、マイクロエレクトロニクスを基盤とし、ソフトウェアで処理される情報伝達の技術によって強化されている。これらの技術は、小型化の進展によって人間活動の全領域でますます広がっている(Castells 2004; Elliot and Urry 2010=2016)。
VRの登場は、こうした議論と重なりつつもさらに一歩先へと私たちを促す。すなわち、VRは、エリオットやアーリが想定したような、小型化されたモビリティーズが物理的な移動を促し、移動中の経験を変容させるだけでなく、物理的にインモビリティな状態でありながら、仮想空間での移動を可能にし、他者とのコミュニケーションに基づく相互作用のネットワーキングを通して体と心が拡張していくのである。
男性よりもVR酔いしやすい女性
では、VRは、すべての人に平等な仮想空間での移動の機会をもたらすのだろうか。残念ながら、現実はそう単純ではない。
一見するとジェンダー中立に見えるデジタル技術にも、実は男女差が存在する。典型的なのが、「VR酔い(サイバーシックネス/VRシックネス)」だ。驚くことに、多くの研究が女性の方が酔いやすいことを明らかにしている(Meeri 2019; Howord and Zandt 2021)。
150人の参加者を募集し、ヘッドセットを装着したVRゲームを最大20分間プレイしてもらった大規模な実験による研究報告がある。参加者はVR初心者で、酔いがひどくてプレイを続けられない場合は中断できるルールを設けた。実験の結果、女性は男性の2倍の頻度でゲームを中断し、VR酔いの強さは40%も高いことが明らかになった(Cramer,2023)。
どうして、VR酔いには男女差があるのか。理由は複合的である。
まず、挙げられるのが製品やテクノロジーの開発現場における、ジェンダーバランスの問題である。製品やテクノロジーの開発は、男性の研究者・技術者を中心として行われていることが多いため、無意識の性差が日常的な製品にも反映されている(大塚・小林,2024)[3]。
機器の設計という技術的な要因が、男女差を増幅していることも明らかになっている(Stanney, Fidopiastis and Foster, 2020)。多くのVRヘッドセットは長らく「男性の平均的な瞳孔間距離[4]」を基準に設計されてきた。調整範囲が狭い機種では、平均して瞳孔間距離の小さい女性が範囲外になりやすく、レンズ間隔と本人の瞳孔間距離の不一致が生じやすい。にじみやピントのズレ、両眼視の乱れがVR酔いを強める。
さらに、生理学的な問題も指摘されている。2023年の研究は、女性のVR酔い感受性が月経周期におけるホルモン(特にエストロゲンとプロゲステロン)の変動に影響されうることを示唆する(Bannigan et al, 2024)。裏を返せば、経口避妊薬の使用によりホルモンが一定であれば、症状が出にくい可能性がある[5]。当然だが、性は多様である。
また、男女差だけでなく、身体的な障がいをめぐっても隠れた不平等性は存在する。VR教育の研究開発や障がい者向けVRの制作などを行う齊藤大将は、2023年に「身体障がい者はバーチャル空間で自由に動けるわけではない――VR活用の障壁ともたらす光」と題した記事を公開している(齊藤,2023)。そこでは、現在注目されているメタバースやVRの活用の大半は、健常者に向けたものと感じられること、デジタル世界に対するインクルーシブデザインやアクセシビリティは忘れられがちなことを整理したうえで、次のように指摘している。
VRでは、物理的移動が困難な方でも、バーチャル空間であれば五体満足の状態のように自由に動くことができるのでは、と短絡的に考えてしまいがちだ。しかし、ジェスチャーのような「空間」をインターフェースとしたやり取りにおいて、腕や指を自由に動かせない人にとっては、かえって障壁となってしまう。さらに、VRヘッドセットは視覚優位の技術であるため、目が不自由な方はまず使いこなすことが厳しいものとなっている。(…)一見、あらゆる可能性を広げているように見えるメタバースやVRだが、その恩恵を受けている人は一部の人たちという認識を忘れてはいけない[6]。
VRには、新たな移動のあり方と経験を拓く可能性がある。他方で、VRを用いた仮想空間による移動経験にも、現実の移動経験と同様の格差が存在していることが見えてくる。社会的・技術的・生理学的に構築されたこれらの格差を、私たちはこれから乗り越えねばならない。齊藤が指摘するように、デジタル空間だから、VR空間だから全ての人を包摂できるということはない。VR空間にも、インクルーシブデザインとアクセシビリティの議論が求められるのである。
仮想空間という救済と現実からの逃避
では、なぜ人は、仮想空間に身を置くのか。そこは移動可能性を拡張するだけのポジティブな場なのか。羊子さんはこう語った。
それでも結局、現実があってこその仮想空間なのかなとは思います。VRを使うと現実から逃れられる気がするし、でも使い終えると現実への否定感が高まる気もします。仮想空間の先には、つねに現実世界がある感覚というか。
哲学研究者 戸谷洋志が『メタバースの哲学』で指摘するように、土地・環境・身体は、私たちのアイデンティティを形作ると同時に、出生時に選択の余地なく与えられるものでもある。私たちは、自分で選んだわけではないものによって、条件づけられ、形成されるという不条理さのなかで生きている。
メタバースはそうした物理空間の不条理さに対する救済となりうる。と同時に、メタバースへの希望は物理空間からの「逃避」でもある。それを踏まえて、戸谷は言う。
不条理から解放されようとすることは、不条理に向かい合うことを拒否し、不条理を受け入れまいとする態度でもある。メタバースがある種のユートピアであるのは、私たちが、自分で選んだわけでないものによって、自らが条件づけられることを、拒否するからだ。この意味において、メタバースにおける「私」は、物理空間における「私」の否認によって動機づけられている、と言える(戸谷,2024:66-67)。
VRは、不条理さからの解放、つまりは物理空間としての現実の否定を伴う。しかし、たとえ現実の否定を伴っていたとしても、そこには確かに居場所がある。物理空間では叶わない移動が可能となるからだ。それと同時に、「仮想空間の先には、つねに現実世界がある感覚がある」と語った羊子さんの言葉を思い出す。彼女は、そのあと「だから、社会福祉のデザインとかが大事だと思います」と続けた。
否定してもしきれない現実と仮想空間を行き来する経験は、自らの逃れられない身体と環境を再可視化する。その結果、個人の努力では乗り越えられない壁を前に、制度へのささやかな期待が生まれる。主体的な移動が困難な状況で、仮想空間における移動を実現し、その結果として「主体性」を問わずに移動できる社会と福祉のデザインを求める、この言葉は重い。
他者の痛みを現実世界に持ち帰る
最後に、VRが有する移動をめぐる希望的側面に触れてこの論を閉じる。
VRは自己のアイデンティティを再構築するだけでなく、他者の視点を自らのものにすることを可能にする。すなわち、他者の生活世界を「自分ごと」として感じ、思考や行動を変える契機になりうる。
映画やテレビとVRの決定的な違いは、「主観で体験できるか否か」にある。第三者として眺めるのではなく、当事者として没入できる。たとえば、DV加害者が、VRで被害者の視点で暴力のシーンを体験した実験があり、被害者への同一化や恐怖の理解が進むこと、女性が恐いと感じている表情をめぐる認知の改善やバイアスが低下することが報告されている(Gonzalez et al 2020; Seinfeld and Arroyo-Palacios 2018)
この知見は、移動をめぐるジェンダー不平等にも応用できる。レスリー・カーン『フェミニスト・シティ』が示すように、都市の移動には数々のジェンダー差が刻まれている。ひとりで移動する女性が直面するリスク――満員電車での不安、夜道の恐怖、性的な視線と暴力にさらされる可能性――は、男性のそれとは明瞭に異なる。本来、こうしたリスク認識は都市計画や交通政策に反映されるべきだが、現実の議論は遅れている。
そこで、女性が移動中に感じるリスクを擬似的に体験できるVRコンテンツを開発し、計画策定や合意形成の現場で活用することは、ジェンダー不平等の是正に資する有力な手立てになるだろう。
移動は、身体と制度が交差する場所で生じる営みだ。VRは、その絡まりを一時的にほどき、別の身体、別の都市、別の視点へと私たちを連れ出してくれる。でも、ヘッドセットを外せば、現実は続いている。だからこそ必要なのは、仮想空間で得た「他者の痛み」や「自己の可能性」を現実に持ち帰り、インクルーシブな技術、ジェンダーに敏感な都市計画、誰もが動ける社会保障といった移動のデザインへと翻訳していくことではないだろうか。羊子さんの移動をめぐる語りと経験が教えてくれるのは、移動の制限を個人に帰さない社会の実現こそが、私たちを真に前へ動かす力となるという事実である。
注
[1] この内容は、2024年1月23日、2025年10月1日に行った聞き取りをもとにしている。
[2] たとえば、2025年に朝日新聞が実施した調査から、全国の政令指定市、県庁所在地、東京23区、中核市の計109市区のなかで回答を寄せた92市区において、生活保護を利用する世帯のうち、車の保有が認められた世帯の割合は、最も多い自治体でも僅か4%超であることが明らかになっている。(朝日新聞,2025年11月3日「車の保有容認、主要都市で最大4%台 生活保護制度の要件どう考える」https://digital.asahi.com/articles/ASTB20BFTTB2OIPE00ZM.html)
[3] VRをめぐる研究は、STEM(science, technology, engineering and mathematics)分野だと言えるが、2020年の統計データによればSTEM分野における日本の就業者数のバランスは男性が87.1%、女性が12.9%となっている。田中若葉・大谷忠(2024)「日本のSTEM人材における女性進出の動向とジェンダーギャップの特徴」『科学教育研究』48(3): 327-336.
[4] まっすぐ前を見たときの、右目の瞳孔(黒目の中心)から、左目の瞳孔までの直線距離のこと。
[5] 性別適合手術、ホルモン療法とVR酔いの関連性についても、注目に値する。
[6] 齊藤は、機械学習という観点から、次のようにも課題点を指摘している。「今後、ジェスチャーやアイトラッキング、表情などを認識するための技術に、広く人工知能(AI)が使われていくことだろう。AIは大量のデータを読み込み、そのなかのパターンを見つけ出す「機械学習」という手法によって性能を向上させていく場合が多い。しかし、そのデータの多くは、障がい者は対象でないことがほとんどだと思われる。AIには大規模なデータセットが必要だが、そこで見つけられるパターンや特徴量は、障がいの少ない人々に偏ったデータセットになることが考えられる」
参考文献
Artaud , A. (1938) Le Théâtre et son double, Gallimard.(=2019, 鈴木創士訳『演劇とその分身』, 河出書房新社, 77)
Bannigan, G. M., de Sousa, A. A., Scheller, M., Finnegan, D. J., Proulx, M. J.(2024)Potential factors contributing to observed sex differences in virtual-reality-induced sickness. Experimental Brain Research, 242(2): 463-475.
Castells, M. (2004) Informationalism, networks and the network society: a theoretical blueprint. Castells, M (ed.) The Network Society: Cross-Cultural Perspective, Cheltenham: Edward Elgar, 7.
Cramer, R (2023) ‘Cybersickness’ from VR headsets hits women more often. ROUTE FIFTY.
Elliot, A. Urry, J.(2010)Mobile Lives. Routledge.(=2016,遠藤英樹監訳『モバイル・ライブズ——「移動」が社会を変える』ミネルヴァ書房, 40).
Gonzalez-Liencres, C., Zapata, L. E., Iruretagoyena, G., Seinfeld, S., Perez-Mendez, L., Arroyo-Palacios, J., Borland, D., Slater, M., Sanchez-Vives, M. V.(2020)Being the victim of intimate partner violence in virtual reality: First- versus third-person perspective. Frontiers in Psychology, 11: 820.
Howord, M.C. and Zandt, E.C. (2021) A meta-analysis of the virtual reality problem: unequal effects of virtual reality sickness across individual differences. Virtual Reality, 25: 1221–1246.
Meeri, K. (2019) Cybersickness: why people experience motion sickness during virtual reality. Inside Science.(最終閲覧2025.10.15, https://www.aip.org/inside-science/cybersickness-why-people-experience-motion-sickness-during-virtual-reality)
Seinfeld, S., Arroyo-Palacios, J., Iruretagoyena, G. ほか(2018)Offenders become the victim in virtual reality: impact of changing perspective in domestic violence. Scientific Reports, 8: 2692.
Stanney, K., Fidopiastis, C., Foster, L.(2020)Virtual Reality Is Sexist: But It Does Not Have to Be. Frontiers in Robotics and AI, 7: 4.
大塚泰子・小林 明子(2024)「『2025年女性役員比率19%』だけが目標ではない 内実ある男女格差是正を」Deloitte.(最終閲覧2025.10.25, https://faportal.deloitte.jp/institute/report/articles/001189.html)
齊藤大将(2023)「身体障がい者はバーチャル空間で自由に動けるわけではない——VR活用の障壁ともたらす光」CNET Japan.(最終閲覧2025.10.25, https://japan.cnet.com/article/35201400/)
田野口遼(2023))「高齢者がVRで“旅行”、障害者にはメタバースで就労支援も 福祉にデジタル導入…「VR旅行」は米メタとも連携」yomiDr.(最終閲覧2025.10.25, https://www.yomiuri.co.jp/yomidr/article/20230227-OYTET50004/)
バーチャル美少女ねむ・リュドミラ・ブレディキナ(2023)「ソーシャルVRライフスタイル調査2023」(最終閲覧2025.10.25, https://drive.google.com/file/d/1KlyzqJbzMU7KFMC8GdjH7YIUotLmxbv0/view)
林考太郎(2024)「ソーシャルVRにおけるジェンダースイッチング動機と要因に関する分析」滋賀大学大学院修士論文.