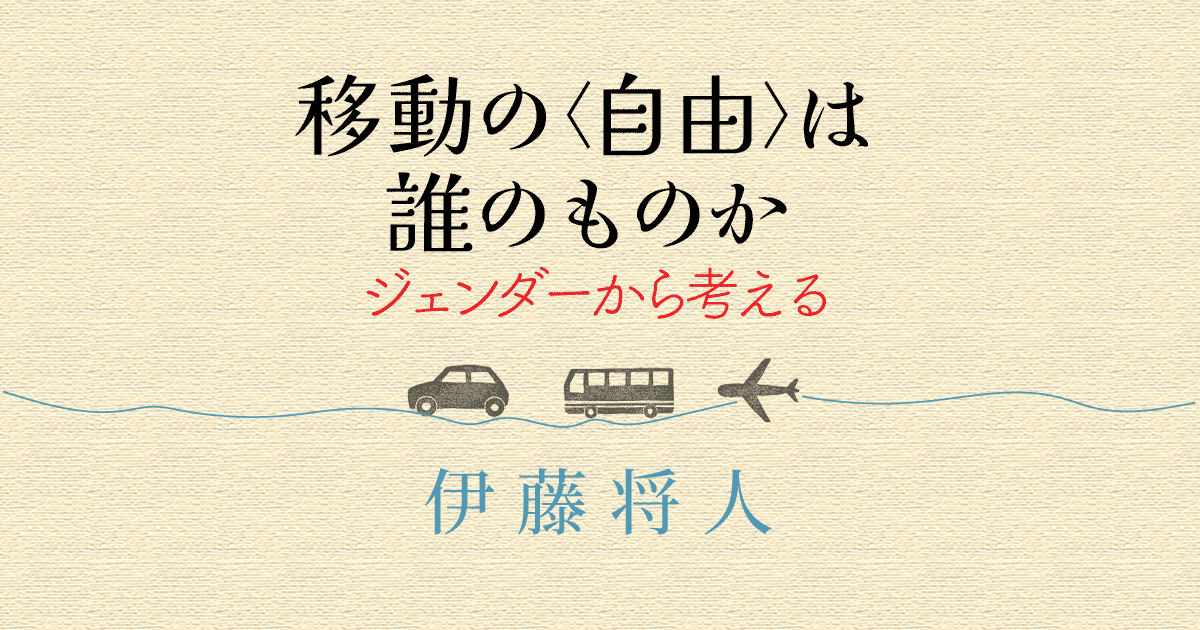移動という日常
これから数回にわたって書こうとしているのは、私が「ジェンダーと移動」について考えてきた/考えていることである。
移動とはなんだろうか。それは、21世紀を象徴するキーワードである。移民、地方移住者、インバウンド観光客、交通弱者[1]、気候難民[2]、すべて移動する人びとだ。
移動するのは、人間だけじゃない。Uber Eatsで運ばれる食べ物、Amazonや楽天の普及で増える宅配物、常時接続の世界(谷川 2022)で止まることのないデータ、新型コロナウイルス感染症のようなウイルス(流行の始まりが5年も前だったことが今や嘘のように感じる)。
私たちの暮らしは移動で成り立っている。移動が止まれば、世界は止まる。地球の自転が止まると、すべてが壊れてしまうように。「現代社会は移動する社会」なのである(Lash and Urry 1994:252)。
2025年5月、移動につきまとう格差や不平等について論じた本『移動と階級』(講談社現代新書)を発表した。はじめての一般読者向けの本だった。どんな感想が寄せられるか、正直、不安だった。
蓋を開けてみると、たくさんの方が手に取り、読んでくれた。お世辞にも取っつきやすいタイトルとは言えない本なのに。学術的な用語が頻繁に登場する、移動というテーマに限定して論じた本なのに。嬉しいよりも、驚きが勝った。
ジェンダーと移動が交差する
本を出すにあたって、編集者さんから「新しい本を出すと、ECサイトのランキングを毎日のように確認するんです」と聞き、私も真似をしてみた。さまざまなカテゴリーに分けてランキング化されている中で、比較的長い期間、1位になっているカテゴリーがあった。それが、「ジェンダー」だった。
最初見たとき、頭のなかで「?」が浮かんだ。たしかに、本のなかではジェンダーに関する節(章ではない)を設けた。しかし、全体に占める割合は1割にも満たない。タイトルだけ見ても、この本にジェンダーと関連する話題がでてくることはわからない。
本を出してから1週間、2週間、そして1か月ほど経った頃と記憶しているが、その時期になってもなおジェンダーのカテゴリーで1位だった。他にも魅力的なジェンダー本はあるというのに。同時期、読者から寄せられる感想も、女性からの「自分の経験や悩みが、そこに重なりました」という声が増えていた。
移動を形作る要因には、いろいろなものがある。年収、国籍、学歴、そしてジェンダー。想像しやすいのは、年収や居住地域だろう。移動をするにはお金がかかる。移動の距離が長くなるほど、より早く移動しようとするほどお金がかかる。いま、ロケットで宇宙に行くためには1人あたり数十億円がかかる。一番遠くに、一番早く移動するから、一番高額というわけだ。なので、お金がある人ほど自身の移動を望むとおりに実現できたり、住んでいる地域の移動インフラ(公共交通機関の有無や頻度、高速道路のインターチェンジとの距離など)が充実しているほど移動しやすかったりする。
年収や住んでいる地域と比べると、男女間で移動の在り方が異なるというのは想像しにくいかもしれない。しかし実は、移動をめぐる差異や不平等を生み出す要因には、ジェンダーに起因するものが多くある。ジェンダーと移動が交差する場面について、いくつかみてみよう。
離れたい、けど離れられない――コロナ禍とDV
ある立場からは社会がよくなったように見えるけど、違う立場からは社会が悪くなったように見える。そんなことは、意外とよくある。物事には、両面ある。両面性は、社会や組織の決まり事(制度や政策)が変わったときに表れやすい。
コロナ禍を思い出してみよう。一部の業種でテレワークが認められ、出社しなくても仕事ができるようになった。これまで家族との時間が取りづらかった人、出勤に2時間もかかっていた人からすると、社会がすごくよくなったように感じただろう。
他方で、コロナ禍ではDVの相談件数が増加した。全国の配偶者暴力相談支援センターと「DV相談プラス」に寄せられた相談件数を合わせると、2020年度は前年度と比べておよそ1.5倍も増加した。1年で1.5倍の増加は異常だ。相談者のほとんどは女性である[3]。
さまざまな理由で家にいたくない人、家族から少しでも長い時間離れたい人にとっては、外で働けないことも、出社せずに働ける家族が長時間家にいることも嬉しくない。それは、恐ろしいことですらある。
社会学者の小ヶ谷千穂(2020)は、こう言う。パンデミックは「ホーム(家や居場所の意味)」が決して「安全・安心」ではなく、不平等なジェンダー関係に基づいて構築された「ジェンダー化された場所」であることを明らかにした、と。
移動のケア――母親たちによる送迎という見えない労働
2025年某日、私は岩手県のある自治体で市議を務める加藤さんと話していた。かねてから調査でお世話になっている方で、私よりも少し年上。市議会のなかでは若手で、大学卒業後にこの地へIターンしてきた。移住政策のこと、結婚推進の是非のこと、公共交通のこと――いつも通り取り留めもなく話していたとき、「最近、地域で新しい移動の問題が生じていて、伊藤さんなら興味あるかなと思って。話してもいいですか?」と、加藤さんが切り出した。
話題は、公立中学校の部活動の「地域移行」だった。私が中学生の頃を思い出すと、とても厳しい数学の先生が、授業以上の厳しさで陸上部の顧問を務め、朝練習にも放課後練習にも顔を出していた。休日の大会にも同行していた。
しかしいまや少子化の影響で学校単位の部活が維持できず、教員の過重労働も社会的問題になっている。そこで政府は、地域のスポーツクラブや企業人、少年団などが指導を担う体制への移行を促している。2026年度以降は、休日だけでなく平日の部活動も「地域化」していく方針だ。
一見すると、教員の負担が軽くなり、子どもたちの交流の輪が広がり、地域との接点を取り戻すこともできる、とても優れた制度に見える。しかし、ことはそう単純じゃない。
部活動が学校の外に移れば、活動の場も学校から離れる。子どもたちは一度家に帰り、親に活動場所まで送迎してもらわないといけない。開始時間は遅くなり、帰宅も自然と遅くなる。加藤議員の市では、親の送迎が難しいことを理由に、部活の地域移行に伴い好きだったスポーツをやめざるをない子どもが出てきている、そういう話だった。
こうした実態は、徐々にメディアでも取り上げられている。長野県下諏訪町の中学2年生の男の子は、母親の由梨佳さんの退勤を職場駐車場で待って車で約1時間の練習場所へ行く。由梨佳さんは「やりたいことをやらせてあげたいので大変だけれどぎりぎり何とかやっている」と話す[4]。
「親が子どものために送迎するのは当然でしょ」、そう思う人もいるかもしれない。しかし、母子世帯や父子世帯であったり、遅い時間まで親が共働きしていたりする場合は、たとえ送迎が週1、2回であっても難しい。地方だと最近は熊が出る。
時の針を巻き戻し、地域のつながりが強い時代だったら、お互い様の関係で送迎をお願いできるかもしれない。でも、今では隣人の顔も名前も知らない地域も少なくない。
負担は、主に母親の肩にのしかかっている。ある研究によれば、母親は父親よりも地域移行に関する強い懸念を示す傾向があるという(林田ほか 2024)。一つの理由は、子どものスポーツ活動を支える過程で母親のほうが大きな精神的・身体的負担を背負ってきたからだ(宮本 2023)。共働き世帯が増えても、性別役割分業の規範は根強く残り続けている。
「公共交通を使えばいい」という意見もある。しかし、電車が走っていない、バスは数時間に一本――そうした地域でこそ、この問題は深刻化する。低所得の母親ほど負担感を強く訴えており、時間だけでなく金銭的な困難も重なっている(林田ほか 2024)。
部活動の地域移行は、教育制度や地域社会の仕組みの問題にとどまらない。そこには、移動をめぐる問題が横たわっているのである。移動のケアは、一体誰が担うものなのか。子どもの移動を支えるという名目のもと、家族という私的領域で、母親たちによる見えない労働が日々積み重ねられている。
グローバル化と戦後沖縄のセックス・ツーリズム
ジェンダーと移動が交差する場面は、国内にとどまらない。たとえば、国境を越える「性の商業化」は、新自由主義的なグローバル化における重要な構成要素となっている(Elliot and Urry 2010=2016:140-141)。
社会学者の小川実紗(2025)は、性をめぐる移動の歴史的な検討から、セックス・ツーリズムにおけるジェンダー・ポリティクス――社会規範に基づく性差が政治的な課題として浮上する局面――を鋭く描き出している。
「セックス・ツーリズム」は売春を目的とした旅行を指し、典型的には先進国の男性が物価の安い国を訪れ、買春することを意味する。南極を除くほぼすべての地域で見られるこの現象は[5]、社会的に高い地位を占める中上流階級の男性たちによって支えられてきた(Bender and Furman 2004)。そして、その裏側には常に女性や子どもといった社会的弱者の搾取があった(Brooks and Heaslip 2019)。
性を提供する側となる女性は、多くの場合「非モビリティーズ」あるいは「強いられたモビリティーズ」のなかに生きる。貧困によって土地に縛りつけられ、移動の自由を奪われ、性産業に従事させられる状況。それが、非モビリティーズである。
戦後沖縄の事例は、この構造的問題を象徴している。小川(2023; 2025)が明らかにするように、占領期には米軍向けの歓楽街が形成され、米兵の移動に伴って沖縄の女性たちの貧困が再生産されていった。「前借金」と呼ばれる制度により店に縛られ、暴力団の監視下に置かれる女性も少なくなかった。やめたいと思っても、そう簡単にはやめられなかった。
沖縄が本土に復帰すると、観光客として沖縄を訪れる本土男性を相手にした、国境を越えないセックス・ツーリズムが広がる。さらに1980~90年代以降になると、フィリピンからの出稼ぎ女性が増加した(小川 2025:181)。異国で性産業に従事する彼女たちに共通したのは、貧困によって移動を余儀なくされる「強いられたモビリティーズ」である。
こうして見ていくと、戦後沖縄のセックス・ツーリズムの担い手は、沖縄で生まれ育ち米兵を相手とする女性、本土男性を相手とする女性、フィリピン女性など、多様な主体が交錯しながら変改されてきたことがわかる。けれども、そのときの社会状況によって、より貧しい地域から女性が移動しているという構造と、観光という移動で沖縄を訪れる男性が女性を性的に搾取するという構図自体は変わらなかった。
性別によって異なる移動の経験
ここで紹介した3つの事例は、ジェンダーと移動をめぐる出来事のほんの一部に過ぎない。人びとがどのように移動するか(どこで、どのぐらいの速さで、どのぐらいの頻度で、など)は、明らかにジェンダー化されていて、ジェンダー化された権力構造を再生産し続けている(Cresswell and Uteng 2008:2)。にもかかわらず、これまで、女性の移動者・移住者に対する理解は乏しく、「移動自体が性別によって異なる経験である」という認識は不足していた(Harzigほか 2009)。
この連載では、さまざまな「ジェンダー化された移動(Gendered Mobilities)」について論じていく。一見すると、移動は誰にとっても平等だと思うかもしれないが、男女間の差異がそこには潜んでいる。ジェンダーによって区別され、再生産される物語、歌、言説、表象を通して移動に付与される意味に注目してみたい。
このテーマについて詳しいイギリスの地理学者で詩人ティム・クレスウェルとノルウェーの交通計画学者タヌ・プリヤ・ウテンが言うように、移動とジェンダーがどのように交わり合うのかを理解することは簡単ではない。なぜなら、そのどちらの概念も多様な意味や権力関係を帯び、解釈をめぐって常に争われているからである。(Cresswell and Uteng 2008:1)。でも、だからこそ、その複雑さと解釈の多様性を論じる意味がある。
正直なところ、この旅路がどこに向かい、どこに辿り着くのかわからない。しかし、焦らずゆっくりと丁寧に、絡みあう移動とジェンダーの糸を解きほぐすことで、見えてくるものがきっとあるはずだ。それは、日常のなかで見過ごされやすい「移動すること」と「移動しないこと」のグラデーションのようなものかもしれないし、もやもやとしたものに少しの見通しの良さを与える新たなまなざしかもしれない。
この連載は、決して最終的な答えを提示するものではない。むしろ問いを重ね、読み手とともに考え、時には立ち止まり、別のあり方を探るための試みである。移動とジェンダーの交差点に立ち現れる小さな違和感や気づきを手がかりに、私たちはどんな社会を描きうるのか。その問いかけから、考えることを始めたい。
*なお、本連載に登場する人物については、調査に協力してくださったモデルとなる方々はいるが、個人が特定されない形で名前や特徴を変えている。ただし、扱うテーマと関連する形ですでに名前が公表されている方や、あらかじめ許可をいただいた方については、実名の場合もある。
参考文献
Brooks, Amm., Heaslip, Vanessa.(2019)Sex trafficking and sex tourism in a globalised world, Tourism Review, 74(5):1104-1115.
Bender, Kimberly., Furman, Rich.(2004)The implications of sex tourism on mens social, psychological and physical health, The Qualitative Report, 9:176-191.
Cresswell, Tim., Uteng, Tanu. Priya.(2008)Gendered mobilities: Towards an holistic understanding, Gendered Mobilities, Routledge:1-12.
Elliott, Anthony, Urry, John.(2010)Mobile Lives, Routledge.(=2016,遠藤英樹監訳『モバイル・ライブズ――「移動」が社会を変える』ミネルヴァ書房)
Forbes(1999)GDP the sex sector(最終閲覧2025年9月8日, https://www.forbes.com/forbes/1999/0614/6312214s2.html).
Harzig, Christiane., Hoerder, Dirk., Gabaccia, Donna.(2009)What is Migration History?, Polity.(=2023,大井由紀訳『移民の歴史』筑摩書房)
Lash, Scott., Urry, John.(1994)Economies of Signs and Space, Sage Publications.
小ヶ谷千穂(2020)「移動から考える『ホーム』――画一的な『ステイ・ホーム』言説を乗り越えるために」『現代思想』48(10):89-95.
小川実紗(2023)『観光と「性」――迎合と抵抗の沖縄戦後史』創元社.
小川実紗(2025)「セクシュアリティ・モビリティーズ――戦後沖縄にみる性をめぐる移動の批判的検討」伊藤将人ほか編『モビリティーズ研究のはじめかた――移動する人びとから社会を考える』明石書店:173-185.
谷川嘉浩(2022)『スマホ時代の哲学――失われた孤独をめぐる冒険』Discover 21.
林田敏裕・醍醐笑部・清水紀宏(2024)「運動部活動の地域移行に対する保護者の態度に影響する要因――社会経済的地位に着目して」『体育学研究』69:299-315.
宮本幸子(2023)「母親がささえる子どものスポーツ――実態と研究課題」『年報体育社会学』4:23-33.
注
[1] 自家用車を運転できず、公共交通に頼らざるを得ない人。特に交通機関が未整備・不便で移動に困難を伴う人を指す。また、交通事故で被害を受けやすい歩行者や自転車。特に子供や高齢者も指す。
[2] 海面上昇や洪水、干ばつなど、地球温暖化や気候変動で住む場所を追われる人たち。具体的には、気候変動により激甚化した災害により住まいを失った人たちや、温暖化による海面上昇や砂漠化により住む場所を失った人たちを指す。
[3] 2020年度分の「配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等」によれば、相談件数の総数129,491件のうち、女性からの相談件数が125,916件、男性からの相談件数が3,575件であった。(最終閲覧,2025年9月7日,https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/data/pdf/2020soudan.pdf)
[4] 信濃毎日新聞(2025)「「今が限界」送迎や見守り、部活地域移行で保護者の負担増 「過渡期」の長野県内で大人も子どもも模索」(最終閲覧,2025年9月7日,https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2025050500614)
[5] タイでは、セックス・ツーリズム産業が約250億ドルの価値を持っていて、国内総生産(GDP)の12%を占めるほどの経済的規模を誇る状況にある(Forbes 1999)。