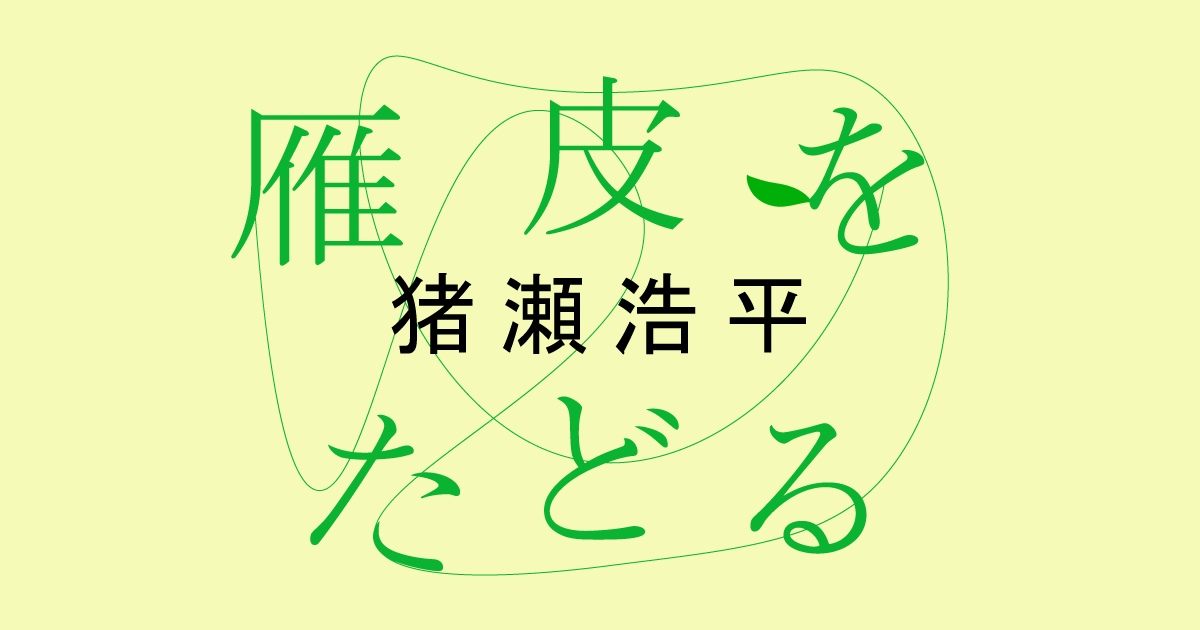雁皮を届ける
御成婚の森の雑木を伐採すると、森には光が差すようになった。その後も朝霧森林倶楽部の人びとが管理作業を続けていくと、森の中に雁皮が自生しているのが見出された。地元出身で、子どもの頃に雁皮の採集をした経験をもつその人は、森の中を歩きながら「ここにはヒノ(地元の言葉で雁皮のこと)が多いねえ」と言った。そのほかのメンバーはヒノ(雁皮)が何か知らなかったが、同じように子どもの頃に雁皮を採集していたシマオカさんはその言葉に応答した。少年時代のシマオカさんは、冬場に集めた雁皮を、村々をまわって種を売り、狸の皮やマタタビなどを買い付けて帰っていくおんちゃんに売った経験があり、「高級紙幣の原料になる」と聞かされていた。
やがてシマオカさんは、御成婚の森に雁皮が生え始めたということを、外の世界に向かって発信し始めた。そのための使者として選ばれたのが、わたしだった。
***
わたしの職場の先輩が中心になって、2014年度に始めた「『農の営み』を通じた新しい価値軸の提示」をめぐる研究プロジェクトには、ジャーナリストなど研究者以外の人も参加していた。その中には、先輩が週末に暮らす埼玉のときがわ町の紙漉き職人であるタニノさんも参加していた。わたしもそのメンバーであり、高知で行う調査の時にはわたしが四万十町を案内し、シマオカさんらと調査メンバーをつなげた。このとき、シマオカさんとタニノさんは出会った。
シマオカさんは2011年から毎年11月に明治学院大学のわたしの授業のゲストスピーカーと、福祉農園での農業塾の講師(百姓先生)をしており、2016年に来た際にはときがわ町を訪問している。11月なのに珍しく雪が降ったその年、シマオカさんはタニノさんの和紙工房を訪れた。細川紙の継承者であるタニノさんの工房の外には、皮を剥いだあとの、楮の白い芯が並べられている。工房の中には剥がされた白皮があり、白皮を塵取りした紙料があり、ノリとなるトロロアオイと混じった紙料があり、そして楮を原料の中心とする紙があった。
シマオカさんはタニノさんに、御成婚の森に「高級紙幣の原料になる」雁皮が生えていると伝えた。タニノさんは、各地の和紙工房が雁皮を必要としているが、国内産はなかなか手に入らず、外国産のものに頼っているところもあるという話をした。
2017年の1月、雁皮があるから、タニノさんに知らせてほしいと言ってわたしが連れていかれたのが、御成婚の森だった。そこでわたしは地元の出身で、1938年のシマオカさんよりもさらに4歳年上のオカモトさんと出会った。[1] 二人の導きで、わたしは御成婚の森を歩き、あちこちに生えている雁皮を確かめ(当時はほかの木との見分けはつかなかった)、御成婚の森の一番上まで歩き、そして下まで降りた。降りた後に、シマオカさんからオカモトさんが満蒙開拓の経験をしていること、同行した父親や叔父などを現地で亡くし、一人で村に戻ってきたことを聞いた。
わたしは雁皮とともに、オカモトさんとオカモトさんの満州での経験と出会った。それから、本来直接つながっていないものが、実はつながっているように感じるようになった。
シマオカさんとオカモトさんが採取した雁皮を託されたわたしは、飛行機で持ち帰り、タニノさんに届けた。
雁皮の栽培
2018年3月にわたしが四万十町を訪ねた時には、シマオカさんは雁皮の栽培を始めていた。雁皮の苗は朝霧森林倶楽部が管理する、地元の小学校の学校林やその周辺に生えているものを集めた。この学校林は2013年から、朝霧森林倶楽部が除間伐の作業を始めた森だ。もともと自生する雁皮があったが、雑木林に光が差し始めると、新たな雁皮がどんどん芽を出していった。そうやって集められた苗を、シマオカさんは所有するヒノキ林に隣接する畑に移植した。北側、東側、南側にヒノキ林があるため、畑には東西側からしか日が差さない。シマオカさんは「日当たりが悪いところに、一定期間西日が入ると雁皮は育つ」と考えて栽培圃場に選んだ。山から土砂が流れてくる砂地であることも、雁皮に適していると考えた。
その年の8月にわたしが四万十町を再訪したときも、シマオカさんは雁皮の畑を案内し、生育状況を示しながら草取りにも精を出していると語った。大きくは育たない雁皮は、放っておくと雑草に覆われる。シマオカさんは、よく研いだ鎌を使い、丁寧に草を刈っていた。
2019年8月は、雁皮の生育状況を確かめたいとやってきたタニノさんも一緒にシマオカさんのところを訪ねた。雁皮は順調に生育し、花が咲いた後に種となる部分も膨らみ始めていた。シマオカさんはその様子を嬉しそうに説明しながら、「お金ではなく楽しみだから、研究になる。おおらかにやるのがいいんじゃ」と語った。
2020年には、朝霧森林倶楽部のハマダさんを中心に、雁皮の種を採集し、苗づくりも始めた。種はその前年に、学校林に自生する雁皮から集めた。それを500個の育苗用ポットに播種した。栽培方法は、雁皮の栽培法を開発した福井県の林業試験場の技術者の資料をもとにし、2019年の11月に同じ技術者の指導を受けている兵庫県西宮市北部、六甲山の北麓地域の森林保全ボランティア団体ナシオン創造の森育成会を訪ね、情報交換をした。
11月に採取した種は、メッシュの袋に入れて土中に埋める。翌年の4月の初めに掘り出し、米の温湯消毒のように55度のお湯につけ1分間温める。それを御成婚の森でとれる赤土と、オカモトさんの炭焼き窯の脇の赤土をまぜた培土――堆積岩がベースで、チャート、粘土も混じっている――に植えると一週間ほどで発芽する。それを丁寧に育てていった。
御成婚の森に最初に定植したのは、2021年3月のことだ。450本植え、1、2本を除き順調に育った。
コロナでなかなか訪問できなかったけれど、わたしは2022年3月に久しぶりに四万十町を訪れ、シマオカさんやハマダさんたちともに御成婚の森にいき、40本定植した。この年は350本近くを御成婚の森に定植した。2023年の3月には、わたしは3歳の長男を連れて行き、四万十川の対岸の集落に雁皮を植えさせてもらった。前年11月にシマオカさんが明治学院大学で行った授業に感動したタバタ君も四万十町で合流し、彼もまた雁皮を植えた。2023年の8月、わたしはボランティア・市民活動実習という授業を受けている学生とともに四万十を訪れた。タバタ君は数日前に四万十に入り、炎天下のなかでハマダさんとともに雁皮を覆っていたヤブガラシを丁寧に取り除いた。
雁皮を出荷したのは2023年が最初だ。御成婚の森で育てた苗180本も出荷した。朝霧森林倶楽部が雁皮を集めているという話を聞き、自生している場所を教える人や、刈ったものを持ってきてくれる人もいた。四万十市の方に延伸していく高速道路の法面に雁皮が生えているのを、同じ場所で正月飾りのシキミをとっている人に教えられ、管理者に許可をとって採取したこともあった。
ハマダさんを中心に、朝霧森林俱楽部の人たちは、種を集め、苗をつくり、育て、定植していった。
雁皮を集めて、皮を剥ぐのもまた一仕事である。楮や三椏とちがって、雁皮は蒸さずに皮を剥くこともできるが、冬場は皮が固いので、釜で蒸し、柔らかくしてから剥いだ。5人がかりで3時間かけて剥いだ白皮は、1.8キロになった。
そうやって綺麗に仕立てた白皮を、朝霧森林倶楽部の人たちはタニノさんに送った。
***
ハマダさんは雁皮に絶対に需要があると考え、若い人たちに育成の仕事を引き継ぎたいと考えている。ハマダさんはシマオカさんの2歳下で、1940年にほとんどが台地に位置する四万十町の沿岸部の地域である興津に生まれた。シマオカさんの通っていた地元の公立高校に1年通ったあと、瀬戸内海にある海員学校に入った。卒業後は貨物船の乗組員になり、国内外の港をまわった。サンフランシスコからアカプルコ、リオデジャネイロ、ニューヨークと、物資を積み換えて運んでいたこともある。オフィサーの資格をとってから、川崎を拠点とする海運会社に就職し、捕鯨船に燃料を運んだ。母校の川崎港に停泊しているときは、都内のあちこちを回った。巨人対阪神のいわゆる「天覧試合」も後楽園球場で観戦した。しかし、船に戻る時間が迫ってきていたので、長島茂雄のサヨナラ満塁ホームランの時には球場を離れていた。中東に行くタンカーにも乗った。40日くらいかけて、中東と日本を往復した。機関士のハマダさんの仕事は、船の機関のチェックだった。海の上なので、故障は許されない。ハマダさんは結婚した後も、家族を四万十町に残し、世界の海を渡り歩いた。59歳でリタイアしたあとは、地元の商工会や観光協会の事務局長をつとめる。この時代に、ともに朝霧森林倶楽部をつくる人びとと出会った。その仕事も70歳でリタイアし、やがて朝霧森林倶楽部に入った。地元は漁村で、仕事場は海。山には縁がなかった。そんなハマダさんは、かつて船の機関を点検していた手で、チェンソーを握ることになった。やがて、雁皮と出会い、その栽培に取り組み始めた。
ちぐはぐなドメスティケーション
シマオカさんが、学校林から苗をもってきて育てた雁皮は途中までは順調に育ったが、あまり太らなかった。なんとか1メートル50センチを超えるくらいまで育ったものを伐採し、皮を剥いだが、そのあとは再生しなかった。当初シマオカさんが考えていた、「 (西側に開けていて)一定時間だけしか日があたらない」、「山から土砂が流れてくる砂地」という条件は、栽培に適していないということが朝霧森林倶楽部の人びとの共通認識になった。太らないことには、皮がたくさんとれず、採集の効率が悪い。太らない雁皮は市場価値がないということになった。それでもシマオカさんは春には雁皮の周りの草を刈った。2025年6月、わたしがシマオカさんと現場を尋ねると、雁皮は草の中で生きていた。
シマオカさんとハマダさんたちが取り組んでいることは、ドメスティケーションdomesticationと呼ぶことができる。ドメスティケーションとは、住まいや家、町、家庭、家族などを意味するラテン語のドムス(domus)に由来する言葉で、人間が関わる環境に動植物が持ち込まれて変化が生じることである(山本2009:3)。G.ラディンスキーは『栽培植物の進化』で、栽培下での植物の進化を①農業が始まって以来、せいぜい1万年以内の出来事であること、②多くの主要作物の祖先が野生種として現在も生育していること、③人類が重要な役割を果たしてきたこと、とまとめている(ラディンスキー2000)。付け加えるならば、地球上の植物が22~26万種、ほ乳類が5000種以上、鳥類が1万種いるなかで、人間がドメスティケーションできている種は少なく、植物だと100科以上だとされる(卯田2021:ⅱ:畑2007)。改訂新版の『世界大百科事典』によれば、栽培されている植物は約2300種とされる。
雁皮は、まだそのうちの一種になっていない。一種になるかどうかのあわいに、雁皮とハマダさんたちはある。
***
ドメスティケーションは、持続し、拡張するプロセスでもある。
シマオカさんがはじめ、ハマダさんが引き継いで極めようとしている雁皮の栽培によって、人間と雁皮の距離は近づく。雁皮を知らなかった朝霧森林倶楽部の人たち、タニノさん、わたし、タバタ君……。その他多くの人たちが、雁皮に引き寄せられていく。
人と雁皮、そして雁皮が育つ環境がどのように変化していったのか、変化していくのかについても詳しく理解ができるようになっていく。かつて炭焼きがされていた雑木の森には、雁皮がよく生えていた。戦後に森林の伐採が進んだことも、雁皮の生育には適していただろう。人びとはそこに一本一本、スギ、ヒノキを定植した。子どもたちは、まだスギ、ヒノキが育たず、光が差し込んでいたその山で遊びながら、雁皮を採取し、それを仲買人に売って小遣いにした。やがてスギ、ヒノキが育っていくと、森は暗くなり雁皮は育ちにくくなった。くわえて、原料として雁皮を使っていた謄写版原紙は、コピー機の普及に伴い次第に生産されなくなった。雁皮を使った和紙の需要も伸びてはいない。
間伐がされず、暗くなった森は保水力を失い、生物多様性を減少させる。シマオカさんはそんな森を「緑の砂漠」と呼ぶ。シマオカさんは森が適切に管理されないことが、四万十川の水量を低下させていると考えた。朝霧森林倶楽部は、そんな「緑の砂漠」を生み出さないために森林保全活動が必要だという、シマオカさんの呼びかけで始まった団体だ。仲間を増やし、管理を進める先に雁皮とめぐりあった。単に経済的な価値があるから、雁皮を栽培するのではない。森を守る事、森が形成するエコシステムを回復させること、その活動の先に雁皮栽培があり、雁皮が健全に育つ森を保全する活動がある。ただ栽培種化をめざすのではなく、人間と雁皮、そして雁皮以外の生物がまじりあい、景観を更新していくことの全体をドメスティケーションとして考えた時、わたしたちは朝霧森林倶楽部の活動の意味を、より深く理解できる。それはどこかちぐはぐさをふくむものであるが、それ自体がドメスティケーションという雁皮を取り巻いて生まれていく人間と自然の蜿蜒たる関係の本質である。[2]
「夢がかなった」
2023年から、紙漉き職人のタニノさんの協力によって、朝霧森林倶楽部が管理作業を行う小学校の学校林をつかった新しい動きが始まった。
計画はこうだ。6月に6年生が、朝霧森林倶楽部のメンバーとともに学校林に自生する雁皮の刈り取りを行う。児童数は10数人で、大人の背丈ほどの高さになった雁皮を、一人が2~3本ずつ刈り取る。そして朝霧森林倶楽部の人たちの指導を受けながら、ナイフを使いながら皮を剥ぐ。剥いた皮に付いた黒皮をとって、白皮だけにする。それをタニノさんのところに送る。タニノさんは、雁皮を煮て、ほぐし、塵取りをし、工房の近くで育てている楮も加えて紙料にし、それを11月に和紙を漉く簾桁などの道具とともに小学校に車で運ぶ。そして6年生たちに指導し、自分たちの卒業証書を漉かせる。文面が筆写された紙が、卒業式の日に子どもたちに授与される。子どもたちが入学当時から親しんできた学校林の雁皮は、タニノさんの地元の楮や、ノリとなるトロロアオイと交わり、子どもたちの成長の証となる。シマオカさんは雁皮をつかった卒業証書が子どもたちに授与されたことについて、「一生の宝物のような卒業証書をもらった」と語った保護者の言葉を、のちにわたしに教えてくれた。
2025年の6月、小学校の学校林をハマダさん、シマオカさんと歩いた。朝霧森林倶楽部が間伐を行ってきた森は、光が入り込んで明るい。伐採した木でつくった遊具に向かって歩くと、ヒノキが並んでいる中に様々な灌木が生えている。朝霧森林倶楽部が植栽したものもあれば、自生したものもある。そこかしこに、小さな雁皮も芽を出していた。
数日後に迫った小学6年生の雁皮の刈り取り作業の話をハマダさんから伺っていると、シマオカさんは「わしの夢がかなった」と野太い声で語った。
雁皮と人間のすれ違いとこすれ合いは続く。それはまだスムーズに進むものではなく、様々なちぐはぐさに満ちている。人の思いがあり、それとは無関係な雁皮やそれを取り巻く生態がある。そのような人と雁皮の両方におこる一連の行動とその変化をあらわすひとまずの証として、小学校の卒業証書はあるようにわたしには感じられる。[3]
人の手も借りながら、雁皮は世界のここかしこに不時着する。そこで蔓延るかどうかはわからない。それでも、雁皮を見出した人に様々な想いを抱かせ、何事かを生み出す。その先にある未来は、不確実だけれども、でも何かに開かれている。2025年の7月5日に87歳になったシマオカさんの「夢がかなった」という言葉をかみしめながら、さらなる夢を追いかける。
注
[1] この話については、生きのびるブックスのWEBマガジンの中の連載「雁皮は囁く」の第2回「御成婚の森のヒノ」を参照されたい。https://ikinobirubooks.jp/series/inose_kohei/1789/
[2] 以上のドメスティケーションをめぐる議論は、Heather Anne Swanson, Marianne Elisabeth Lien, Gro B. Ween編のDomestication Gone Wild: Politics and Practices of Multispecies Relations(野生化したドメスティケーション――多種関係の政治と実践)の序文“Naming the Beast—Exploring the Otherwise”「獣を名指す――他なるものの探求」を参照した。
[3] 重田眞義は、ドメスティケーションをめぐる議論において、ヒトの意図性にのみ注意を払うのではなく、関係を通してヒトと植物の両方におこる一連の行動とその変化をまとめて「症候群(シンドローム) 」として捉える見方を提示する(重田2009)。
参考文献
卯田宗平(編著)2021『野生性と人類の論理――ポスト・ドメスティケーションを捉える4つの思考』東京大学出版会
楳原寛重 1940「雁皮栽培録」関編上掲書、85-93
楳原寛重 1940「続雁皮栽培録」関編上掲書、94-108
日下部兼道、北西敬二 1940「雁皮と其の人工栽培資料」関彪編『雁皮聚録』丸善株式会社、68-84
重田眞義 2009「ヒト――植物関係としてのドメスティケーション」山本紀夫『ドメスティケーション――その民族生物学的研究』国立民族学博物館:71-96
畑啓生 2007 「生物による栽培――沖縄のサンゴ礁におけるクロソラスズメダイの藻園」『エコソフィア』19: 64-69。
ポーラン,P 2003『欲望の植物誌――人をあやつる4つの植物』西田佐知子訳、八坂書房
柳橋眞 1998「楮と漆の仲間」『季刊和紙』15:2-3
山本紀夫 2009「はじめに」山本紀夫『ドメスティケーション――その民族生物学的研究』国立民族学博物館:1-14
ラディンスキー,G 2000『栽培植物の進化――自然と人間がつくる生物多様性』藤巻宏訳、農山漁村文化協会
Heather Anne Swanson, Marianne Elisabeth Lien, Gro B. Ween (eds) 2018Domestication Gone Wild: Politics and Practices of Multispecies Relations. Duke University Press.