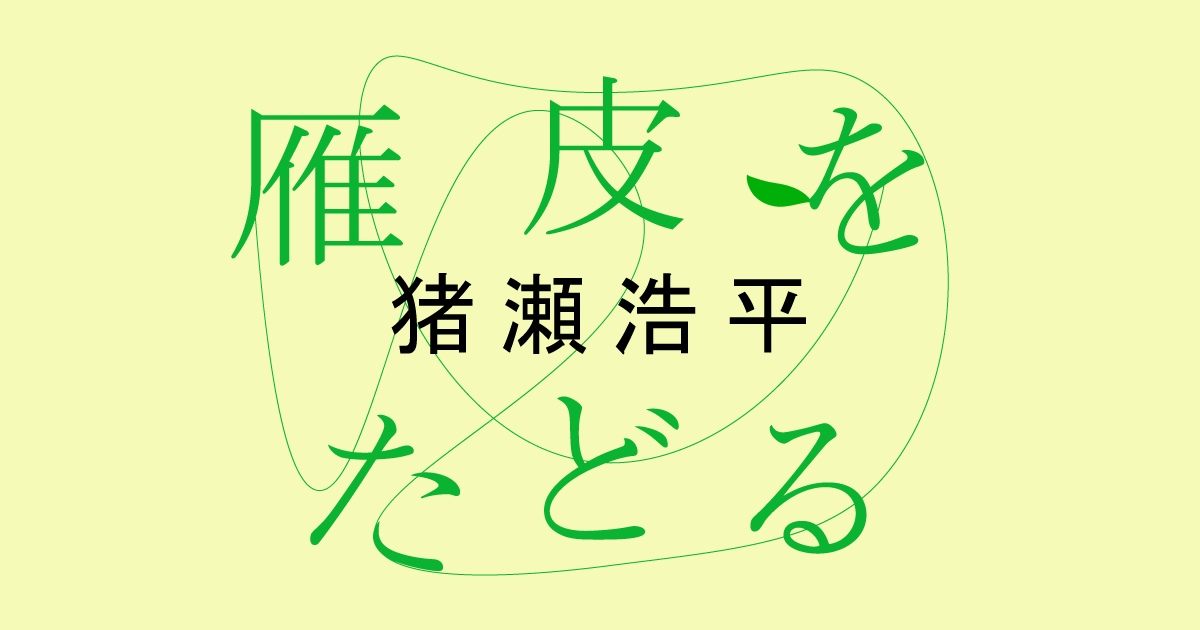雁皮とともに世界を知る
雁皮をたどる行為は、わたしにとって、詩人へのあこがれに似ている。
描きたいことはあり、詩でそれを表現しようとするのだけど、言葉だけがとりとめもなくならぶ。言葉は増えていくけれど、核心にはたどりつくことはない。余計なことばかりを連ねているように思われる。
雁皮をたどるのも同じだ。たどった先にあるのは、いまのところ、雁皮を使った和紙の職人になることではない。雁皮の紙を使った美術作家になるわけではない。もしそれをめざすことになったとしても、充分に雁皮を使いこなすことができるのは相当の長い時間を経た後だろう。人類学者として、わたしは雁皮を追いかけているが、雁皮のすべてを俯瞰的に描くことなどそもそもできず、ただ追いかけながら出会った断片を記すしかないと思っている。雁皮を追いかける。追いかけるが、追いつくことはできず、いつも逃れていってしまう。あとに足跡のような言葉が残る。
越前鳥の子紙が、2025年12月にニューデリーで行われるユネスコの政府間委員会において無形文化遺産「和紙」に追加登録されることになった。その主原料は雁皮である。雁皮を使った紙の評価が高まり、雁皮の需要は高まる。しかし、栽培は簡単ではないため採集に頼るばかりであり、そして採集する人も、採集する場も減っていく。かつてあった場所を探しても、生えていないことがあり、見つかったとしても、望むような太ったものではないことがある。海外産の雁皮も輸入されているが、それが日本でとれる雁皮と同じ品質ではない。もともと違う品種なのだとも言われる。朝霧森林倶楽部の雁皮を使った紙が、アメリカに輸出されたという話が聞かれるが、雁皮自体、生産は必ずしも軌道にのっているわけではない。雁皮はグローバルな資本主義に取り込まれてはいない。人間の欲望や市場の需要と、雁皮の関係はちぐはぐなものだ。稀少性の予感は生むが、あくまで予感に留まる。雁皮から生み出される和紙の価格自体が必ずしも労働に見合うほどは高くないため、原料が稀少だとしても価値があがるわけではない。
雁皮を追いかけていくうちに、思わぬ出会いがある。
わたしはこの夏、今年の3月に山火事に見舞われた場所で、雁皮が芽を出しているのを見た。まだ灰が残る山肌に、他の先駆植物とともに雁皮がいくつも自生していた。猛暑の青い空の下で、岩石を背負い黒い地面から赤みがかかった茎に、小さな黄緑色の葉っぱを互い違いにつけた20センチほどの高さの雁皮がすっくと立っていた。風にゆれる姿を見ながら、わたしは想像する。雁皮が生え、育つことによって、雨が降った時の土砂の流出を少しだけ抑えられるようになる。雁皮はやがて昆虫や鳥類の止まり木となる。虫や鳥が運んでくる様々な種子のなかに、大きくなる樹木の種子も含まれているだろう。樹木が育っていけば、雁皮はどんどん目立たなくなっていく……。

わたしは雁皮を採集する人びとや、雁皮を育てようとする人びと、そして雁皮を使って紙を漉く人を追いかけ、その人たちとともに雁皮で何ができるのかを考えていた。雁皮を使い、何事かを自分がデザインする意識だった。しかし、この焼け跡では、雁皮が森を再生しようとし、ケアし、デザインする主体の一つであった。それも、人間がこの山をデザインすることを考えるよりもはるかに早く[1]。もともと雑木林だったこの山は、現代の人間にとって利用価値がなくなっている。この森の再生は、雁皮やそのほかの植物、菌類、動物、鉱物、土壌、そして風や雨とともに行うべきものなのだ。人間はそのうちの一つに過ぎない。
そんなことを思った。
わたしたちは、雁皮をグローバルな資本主義のなかで付加価値の高い商品として流通させることも、科学技術を使って雁皮の生育を管理し、資源化していくことも十分に実現していない。その一方で、気候変動のように、わたしたち自身の文明が、わたしたちの生きる環境の変化を引き起こしている。わたしたちは、そのままならなさにたじろぐ。そんななかで、雁皮はただ生きる。そのただ生きる雁皮とともにいかに生きるのか。雁皮で紙を漉くことは、森を維持すること、再生する営みにもつながり得る。そしてそれは、雁皮自体をいかにケアするのか/持続可能な形で採取できるようにするのかという問いだけでなく、雁皮が他の生命やその他の存在とともにその生育環境をケアできるようになるのかという問い、そしてその傍らにあるものの一つとして人間がどう存在できるのかという複数の問いにもつながる[2]。
そんなことを考える。
雁皮のことが少しずつ分かっていくにつれ、雁皮にからまったもののことも少しずつ分かっていく。雁皮を知るのではない。雁皮とともに世界を知る。
核心にたどりつけるかはわからない。しかし、核心にたどり着けなくても、わたしたちは多くのことを知ることが出来る。言葉は積もる。落ち葉が堆肥となるように様々な微生物のような存在と交わって発酵し、私よりも先に生きる生命を纏う。
雁皮はもう始めている。それをおずおずと追いかける。
雁皮の変身、雁皮の手触り
2025年10月、埼玉県のときがわ町の和紙職人であるタニノさんの工房で、雁皮の紙を漉かせてもらった。
今回、自分たちで調達した原料を、工房に持ち込むことにした。8月に朝霧森林倶楽部の方々と採取させてもらった御成婚の森の雁皮だ。2015年に雑木を伐採し、光を入れた結果雁皮が芽を出した。2024年に繁茂するシダを刈り、さらに多くの雁皮が生えた。樹齢3年~10年程度の雁皮を、根っこから10センチメートルのところで切った。朝霧森林倶楽部のハマダさんの考えで、切り株から新芽が出ることを期待し、切り口から腐らないよう薬を塗った。この日は太さがまちまちの雁皮をだいたい30本採集した。
そうやって採集した雁皮を釜で蒸す。蒸し上がったら、雁皮の端から端までカッターナイフで一筋の切れ目を引いていく。切り口か外皮がスルスルと気持ちよく剥がれていった。緑色だった中身は、黄色く染まっている。次に、芯から分離された黒皮の表皮を手で取り除く。取り除かれた状態を白皮という。表皮がとりにくいところは、爪やステンレスのヘラを使って落とした。この作業の後、紐にぶら下げて乾燥させる。約30本の雁皮から剥ぎ取られた白皮は、湿り気があって、少し焼き芋のような匂いがした。8月の猛暑期の四万十は、それでも40度近くまで気温が上がる関東や関西に比べると十分に涼しく、32度だった。皮剥ぎ作業には、わたしと、わたしが所属している明治学院大学の学生たちに、岡山から手伝いにやってきた人びとも加わり、おしゃべりをしながら進んだ。後日、この日に仕上がった白皮は1.6キロだったと、ハマダさんが教えてくれた。
ハマダさんから、そのときの白皮がわたしの家に送られてきたのが9月上旬のことだ。宅急便の品名には「樹皮」と書かれていた。これが、紙を漉く原料である。タニノさんから作業の前日に水につけておくように言われていたので、出発前に45リットルのビニール袋に雁皮を入れ、風呂場で水を入れた。そして破けないよう袋を二重にして、車に乗せた。
翌朝、車でときがわ町へ向かった。予定よりも早く出たが、途中で小学生の通学時間にあたり、信号でたびたび止まった。結局予定の時間ぴったりに、タニノさんの工房に到着した。学生のタバタ君とは、現地で合流することになっていた。彼は、2023年の3月にわたしと同じタイミングで四万十に行って以来、朝霧森林倶楽部の活動にも何度も参加している。
工房では、すでにタニノさんのところで紙漉きを学ぶ3人の若い女性の職人たちと、工房で和紙の原料としてもっとも使っている楮の「かずひき(楮ひき) 」をする80代の近隣の農村出身の女性、そしてパートナーのゲンさんが朝の作業を始めていた。「かずひき」は、水につけて柔らかくした黒皮から、包丁をつかって外皮をとりのぞき、白皮だけにする作業だ。ゲンさんに教えてもらいながら、持ち込んだ雁皮をまな板にのせて「かずひき」をやってみた。作業を始めて少し経つと、最寄り駅に到着したとタバタ君から連絡があり、やがて彼も合流した。夏に行った外皮の作業が丁寧だったため、かずひきの作業は10分も経たないうちに終わった。
次の工程は、かずひきが終わった白皮を大釜で煮熟(煮て不純物を取り除き、繊維を柔らかく)する。草木灰のみを使う伝統的な方法もあるが、この日はソーダ灰を使った。アルカリ性のソーダ灰の作用で、雁皮に含まれるリグニンなど不要な成分を溶かし出し、繊維を柔らかくするのが目的である。茶色く濁った釜の中を、白い雁皮が泳ぐ。30分に1回天地返しをしながら2時間、煮熟した。煮熟が終わると、一晩水に晒し、あくを抜くという工程が待っている。
翌日は作業に来られないため、わたしたちは、工房にある別の雁皮でこの先の作業を体験させてもらった。これはハマダさんからタニノさんに別便で送られてきた雁皮で、すでに煮熟と晒しが終わっている。あく抜きされた雁皮は、ひっぱれば繊維が切れるくらいに柔らかくなっていた。水の中に入れると、雁皮の繊維が少しずつ広がっていく。それを両手でつまみながら、目で識別できる、黒く細かい塵やゴミを取り除いていく。時には細い竹の棒で繊維をからめながら泳がして、確認もする。作業しながら、その柔らかい手触りが余韻のように残った。今まで漉かれた紙か植物としての雁皮しか触れてこなかったわたしには、新たな雁皮との交わりの経験だった。この作業には、器用さは必要ない。むしろこの地道な作業を黙々と続ける根気強さが必要なのだ、とゲンさんは語った。
塵もまた雁皮の一部であり、タニノさんはそれを捨てずに溜めておいて、紙に模様を作るときに使う。

17時に終業の時間となり、わたしたちも帰宅することになった。自宅まで車のハンドルを握りながら、繊維を水の中でつまむ感覚がたびたびよみがえった。ときがわ町の水は紙漉きに合った軟水であり、下流よりも水が冷たい。冷たい水によって、楮や三椏、雁皮などの繊維は締まる。黙々と働く職人の女性たちの姿を想いながら、その冷たさのなかで行うかずひきや塵取りが、いかに根気を要する仕事かを理解した。
作業場のリズム、水を操る仕事
翌週、ふたたびときがわ町に向かった。この日は鉄道を使い、何度か乗り換えながらタニノさんの工房へ向かうために八高線の明覚駅に着いた。タバタ君とは途中の高麗川の駅で合流した。東京から離れる移動なので座っていけると思っていたが、どの路線も通学する高校生が多く、また東京に向かう列車に比べて車両が短く、ほとんどの時間立ちっぱなしであった。明覚からバスにのり、工房に近いバス停まで移動する。この日は小雨が降っていた。
ようやく涼しくなった。山の麓にあるときがわ町の空気が爽やかだった。
今日は繊維を叩いて細かくする作業をすることになっている。この工程の前に、本来であれば、塵取りを二度三度行う。一通り終わらせ、繊維を冷蔵庫に入れて、翌日取り出してまた塵取りをする。そうやって、不純物のない綺麗な紙ができる。一週間前にわたしたちは塵取りを一回しかしていない。そのときの雁皮に、わたしたちが持ち込んで煮熟したあと工房の若い職人たちが塵取りしてくれた繊維を加え、叩解作業に入った。だいたい60センチ四方の木の板の上に煮熟された雁皮をのせ、四角い木の棒で叩く。繊維を細かくするのが目的だ。長い繊維が塊としてのこっていると、次のなぎなたビーターという機械の工程で繊維どうしが絡みついてダマになってしまうのだ。ゲンさんがまず見本を見せてくれた。トントントントンとリズミカルに叩いていく。その横で職人たちが流し漉きをしている水の音が響く。叩いた雁皮の塊が薄くなったところで、餅つきの際に餅を返すように、雁皮を返し、また叩く。タバタ君とわたしは交代しながら、15分ほど叩いた。
そうやって叩いた雁皮を、今度はなぎなたビーターに投入する。なぎなたビーターは、ドラムの中になぎなた状の刃物が回る機械であり、その回転によって流れるプールのように水流をつくりだしている。水槽の中を雁皮が泳ぎながら、さらに細かくなっていく。本来、なぎなたビーターは繊維が長い楮に使われ、雁皮は繊維を圧し潰すホーランダービータという機械にかけるのだそうだ。今回は量が少ないため、なぎなたビーターを使った。
スムージーのようになっていく雁皮のなかに、塵をみつけるとそれを掬う。手で掬うと雁皮の繊維がまとわりつき、しばらくすると固まった。ときどきゲンさんがボウルに掬って状態を確認し、15分ほどで作業が終わる。雁皮を受けるためのザルを置いたあと、水槽の栓を抜く。楮と違い、雁皮は繊維が細かくザルから水が抜けるのに時間がかかった。
雁皮が紙になるには、繊維を沈殿させることなくまんべんなく分散させるとともに、とろみをつけて簀の上での滞留時間を長くするため、「ネリ」が必要である。ネリは、花オクラとも言われるトロロアオイの根っこを、一晩漬けて溶け出した粘液である。タニノさんはそれを自分で栽培しており、11月に収穫する。紙漉き職人の中には薬を使って保存する人もいるそうだが、タニノさんはハーブ・エキスとともに冷凍保存し、一年中使っている。だからタニノさんの工房のネリは、とてもいい匂いがした。
水をためた漉き舟に雁皮を入れて、竹の棒で攪拌する。そこにネリを入れてさらに攪拌する。ゲンさんの手が操る竹の棒からは、バシャバシャとリズミカルな音が響いた。攪拌しながら、水の滑らかさを見て、ネリの効き方を調整する。紙漉きとは水と対話する仕事なのだ。

ゲンさんが溜め漉きを実演した。まず桁と呼ばれる木枠に、竹でできた簀を挟み、金具で留める。簀桁を立てて、漉き舟に入れる。雁皮とネリが混じった水を汲む。すこしだけ波がたつように、しかし水がこぼれないようゆっくりと縦にゆすり、横にゆする。そうすることで雁皮の繊維と繊維が絡まる。水が落ちるのを待つ。そしてまた水を掬い、同じようにゆすり、待つ。
実際にやらせてもらうと、まず簀桁を漉き舟に入れるのが難しかった。角度やリズムを間違えると、簡単にヨレがでてしまう。一回目にうまくいったとしても、二回目失敗するとまたそれが跡になってしまう。これまで楮の紙漉きを体験したことはあったが、それに比べれば難しく、雁皮だけで漉く場合は小さなミスが仕上がりに大きく影響することが分かった。タニノさんがやってきて、「半円を描くように」とタバタ君に水の汲み方を教えた。タニノさんは、タバタ君と向き合って、縦へのゆすり方、横へのゆすり方を教えた。水がどの程度抜けているのかは水滴を見ながら判断するということだが、わたしにはまだよくわからず、言われたタイミングで簀桁をゆらす。
漉き終わった後、金具を外し、桁から簀を外す。簀を左手でもちながら、ひっくり返し、不織布の上に置く。水分を含んだ紙は簀に張り付いて、ひっくり返しても落ちない。不織布の上に置く際にはあまり力を入れすぎると跡が残ってしまう。不織布に紙が残るよう注意しながら、簀を剥がす。ここで思い切りよくやれないと、せっかくできた紙がヨレてしまう。次に漉いた紙を重ねるため新しい不織布を置く。
「雁皮紙はとにかく優しく扱わないと駄目だ」と聞いていたが、様々なポイントで繊細さを要求される作業がある。簀桁をどのように漉き舟に入れるのか、水をどれだけ汲むのか、どのような加減でゆすり、漉きあがった紙を不織布にのせ、乾いたあとに不織布から剥がすのか。それぞれ触覚的、視覚的、聴覚的に知覚する部分があり、それを「半円を描くように」といった言葉を手掛かりにしながら、組み合わせつつ実践していく。
一日の作業を通じて、ただ平滑で美しい紙にすることの難しさだけ、十分に理解できるようになった。
雁皮の紙に刷る:わたしたちのエージェンシー
漉かれた紙が不織布をはさんで、重ねられていった。20枚を超えたところで、水抜き用の台に移動する。木の板と板との間に紙を挟み、その上に枕木を何本かのせ、ジャッキで圧力をかけていく。ゲンさんは水の滴りかたを見ながらジャッキを調整した。10分ほどたつと水が抜けて、半分以下の厚さになっていた。
そこから一枚一枚めくりとって、ガスの直火で温めた乾燥台に貼っていく。刷毛をつかって、空気が入らないよう注意する。乾燥したらそれを一枚一枚ペリペリと剥がしていく。
ついに、わたしたちの紙が完成した。ヨレがない紙はなく、また塵もまだとり切れていない。商品のクオリティにはほどとおい。それでも、得るものは大きかった。ただこの一連の経験をすることによって、美しく、平滑な紙を、同じ質で漉き続けるためにいかに高い技が必要とされているかを体感的に知った。この技術は、自分たちが容易にたどり着くことのできない高みにある。同時に、その高みを目指さない「雑な紙」であればもしかしたら、ありあわせの道具で自分でも漉けるのではないかということも考えた。
タバタ君は、朝霧森林倶楽部の人たちのところに何度も通い、雁皮の植え付けから草取り、刈り取りにまでかかわってきた。タバタ君は、雁皮の紙を用いてある構想を練っていた。ローカル鉄道を愛する彼は、四万十川流域を走る予土線を盛り上げることに問題意識をもっており、予土線の走る風景を雁皮の紙に残し、展示できないか考えていた。それを知ったタニノさんは、わたしたちの漉いた紙を使って、工房のレーザープリンターで印刷することを提案してくれて、さっそく実験してみることになった。タニノさんがいうので、その場でアイロンをかけた。プリンターは厚紙設定で出力した。印刷したのは、2022年にコロナ禍を挟んで初めて四万十を訪問した際に写真家の森田友希が撮影した、雁皮の苗。ハマダさんが種から育てたものだ。
プリンターを通して出てきたイメージは波打っていた。紙のヨレた部分にトナーがのらず、そこだけかすれている。雁皮の繊維や、塵、簀桁の目、わたしたちが乾燥させるときにつかった刷毛の動き、プリンターの癖などが、印刷上のノイズとして表れていた。パルプ加工された紙ではこうはいかない。たとえば、パルプでつくられたコピー用紙に印刷するとき、特にトラブルがおきなければ、パソコンにあるイメージがそのまま紙に出てくる。その意味では、プリンターも、紙も透明な存在になる。パルプになる前の木々の存在感を感じることはない。一方、わたしたちの不完全な紙には、雁皮自身を含めた雑多なものの存在感が顕われていた。それは、不完全な生がからまっているこの世界を表しているようだった。
少なくともわたしが漉くのは、純なる紙ではなく、この「雑なる紙」なのだ。そんなことをおもった。

注
[1] 雁皮が先駆植物であることの意味については、別稿で考察したい。一点だけ予示すれば、雁皮の種の発芽率の低さと、長年にわたって細々と発芽するその性質が関係しているとも考えられる。この点についての着想は、今井三千穂氏の論稿に与えられたものだ[今井2025]。なお、森林生態学的に雁皮について考える研究者がいれば、様々伺いたいことがあり、連絡をお待ちする。
[2] この雁皮と紙-森-その他の存在-人間というつながりについて、ロン・ワッカリーがモノのデザインの「関心とケアの領域」を考える際提示した協議体という概念が示唆を与える。以下、ワッカリーの文章からの引用。
協議体の目的は、非人間が積極的に参加できるようにする方法、および非人間の多様性や意見の相違、重なり合う関心を代表する方法を探し出すことである。そうすることでデザインの世界で関心とケアの問題の存在感が高まり、モノのデザイナーから、あるいはモノをデザインする行為から、関心とケアの問題を簡単に排除できないようにすることができる。[ワッカリー2025:279]
今回の議論において、関心とケアの対象は雁皮であるとともに、その生きる地となる森に浸透していく。
参考文献
今井三千穂2025「ガンピの人工栽培;増殖法と栽培について」『和紙文化研究』31;12-29
ワッカリー,ロン2025『ポストヒューマニズムデザイン――私たちはデザインしているのか?』(森一貴・水上優・比嘉夏子訳)、明石書店