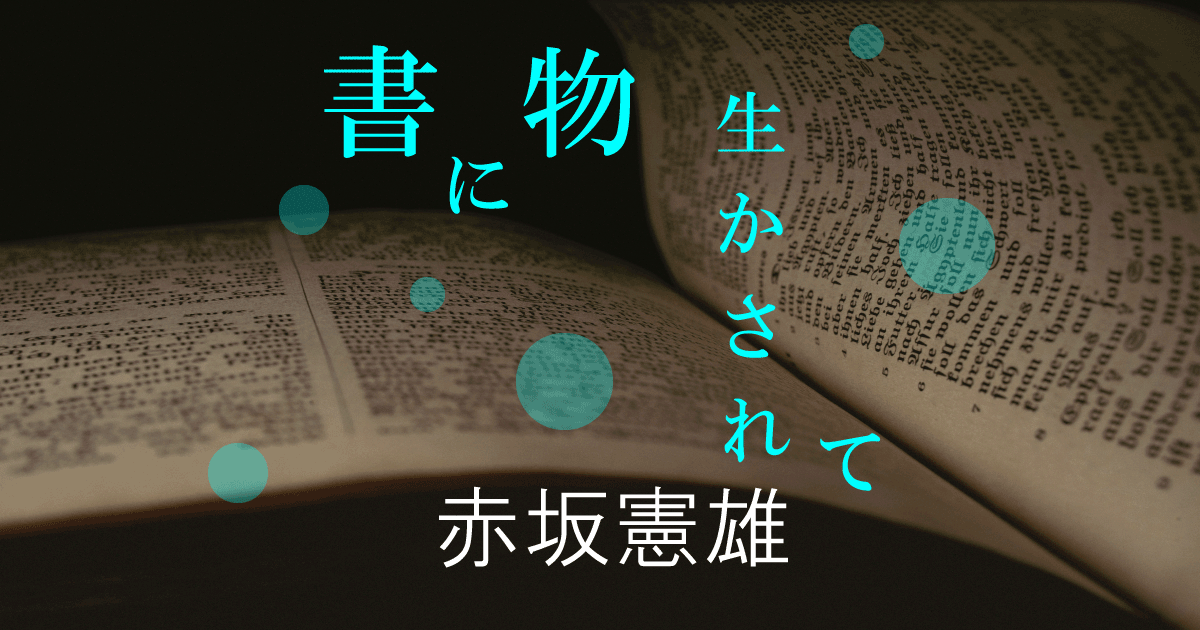いまほど子ども向けの出版物があったわけではない。まだ貧しい時代だった。やがて、近所の学園通りがアスファルト舗装されると、東京オリンピックがやって来る。その、ほんの少し手前であった。給食は脱脂粉乳のなんだか生臭いミルクと、うすい食パンが数枚、そして、わずかなおかず。しなびたランドセルに忍ばせたパンの切れ端を、わざわざ土まみれにして、競いあって食べたことがあった。学校帰りの、友だちの家の庭先での、小さなマツリのような光景である。なんともささやかな冒険のかけら。奇妙な昂揚感だけが思いだされる。九歳くらいの男の子の脳内風景など、もはやたどりようもない。
谷川雁の『意識の海のものがたりへ』に、あらためて触れてみたい。男の子がもっとも魔術の世界の近くにいて、幻想に満たされた季節を生かされているのは、小学校の三年生のころだ、という。谷川は書いている、「怖かった外界は、木も小川も動物もたわむれる相手になった。怪物だって友だちなのだ――そういう男の子の季節がわかりますか」と。正直にいえば、とてもよくわかる、わかり過ぎるくらいにわかる。大人たちの庇護のまなざしから逃れて、どこか頼りなく浮遊しているような、そんな時間がたしかに存在した。
そのころ読んでいた本が、冒険や旅の物語ばかりであったはずはないが、思いだせない。記憶をまさぐるうちに、思春期にさしかかる以前に読んだ本の主要リストがぼんやり浮かんでくる。二人の小説家の名前が楕円の焦点のように見えてくる。マーク・トウェインとジュール・ヴェルヌだ。『トム・ソーヤーの冒険』『ハックルベリー・フィンの冒険』『王子と乞食』、そして、『十五少年漂流記』『八十日間世界一周』『海底二万里』『地底旅行』など。むろん、作者の名前などは知らなかった、まるで興味がなかった。ただ、図書室で冒険や旅や漂流といった言葉を見つけると、借り出して読んだだけのことだ。本には作者の名前がくっついていることに気づいたのは、ずっと後のことである。
さて、ここで取りあげてみたいのは、『トム・ソーヤーの冒険』である。正直に書いておけば、この小説の細部はほとんど覚えていない。たったひとつ、トムが女の子と、どこかベンチに座ってファースト・キスを交わす場面があったはずだが……、と思う。読まずに思い出語りだけをしようかと考えていたが、記憶は大事にしながらも、やはり読んでみたほうがいいのかもしれない、と思いはじめている。
そこで、新潮文庫版の『トム・ソーヤーの冒険』(大久保康雄訳)を手に取って、驚いた。わたしが読んだのは完訳ではなく、子ども向けに編まれた簡約版であったはずだが、みごとに何ひとつ覚えていなかった。『ロビンソン漂流記』だって、じつのところ、覚えていたのはいくつかの場面にすぎない。いや、大人になってから読んだ本だって、儚いほどに細部の記憶などあいまい、かつ茫漠としたものばかりではないか。本との出会いはまさしく一期一会、夢か幻のような体験なのかもしれない。たんに読んで楽しむのではなく、批評や研究の対象となったとき、本というものは劇的に姿を変えてしまうのかもしれない。それを哀しむべきだとは思わないが、何か引っかかるものは残る。
ところで、たぶん六十年振りに読んだ『トム・ソーヤーの冒険』はおもしろかった。読書の快楽が詰まっている。そして、気づかされた。トムとハックの冒険の書はさまざまに、わたしの身や心のなかに影を曳いているのではないか。
接吻という言葉が教室でひそかにはやったことがある。小学校四年生、つまり十歳のあたりだ。はやらせた張本人がわたしだった。接吻って、なあに、という謎かけ。その意味を知る男の子はいなかった。すかさず国語辞典を見せて、ひとしきりはしゃいだ。いま試みに広辞苑を覗いてみる、「 (幕末に作られた語)相手の唇・頬・手などに唇をつけ、愛情・尊敬を表すこと。くちづけ、くちすい、キス」と見える。どんな説明が、子ども向けの国語辞典には書かれてあったのか。なにしろ、大人たちがキスをする姿など一度だって見たことはなかった。念のために書いておくが、わたしはまるでませた少年ではなかった。性に目覚めるすこしだけ手前にいた。いつ、どこで接吻なる言葉と出会ったのか、ずっとわからずにいた。
新潮文庫版の『トム・ソーヤーの冒険』には、こんな場面があった。
やがて少女は、すこしずつ抵抗をゆるめて手をおろした。いまのやりとりで上気した顔を、上を向けてきて、そのままじっとしていた。トムは、その赤い唇に接吻した。
少女が顔を近づけて、「わたしは――あなたを――愛してるわ!」と囁いて、逃げていった。その、すこしあとに続く場面である。十歳のわたしが読んだ、その場面にも、きっとこの接吻という言葉があったのだ、と思う。ベンチではなかった、教室の隅っこだった。ファースト・キスでもなかった。トムは早熟な男の子で、いくらか狡猾に、女の子の抵抗をほどき、小さな罠にかけることだって知っていた。ともあれ、わたしは接吻という言葉を、ほんの偶然によって仕入れたのだった。そうして、その魅惑的な言葉につかの間夢中になったのだ。世界は秘密に満たされている。どれほど子ども向けという名の検閲のヴェールをかけたところで、擦り抜けるものはある。本には未知への扉が、いたるところにひっそりと隠されている。
それでは、いまという時間に身を置いて、わたしは『トム・ソーヤーの冒険』のどこに心惹かれるか、と問いかけてみる。きっとそれは、少年の感受性の網に引っかかったものとは、微妙に、また大きく違っているはずだ。六十年の時の隔たりが横たわる。たとえばそこに、若いころ夢中になって追いかけた異人や境界といった知のフィルターがかかっているとしても、仕方がないことだ。
ハックルベリーの描かれ方など、まさしく共同体の内なる異人そのものではなかったか。村の浮浪児のハックルベリーについては、こんな風に紹介されていた。ハックルベリーは大酒飲みの息子で、村の母親たちからは毛虫のように嫌われ、恐れられていた。というのは、彼は怠け者であり、乱暴かつ下品で、たちの悪い小僧であったが、それにもかかわらず、子どもたちはみな、彼を尊敬し、付きあいたがり、彼のようになりたいとさえ願っていたからだ。
こんな魅力的なプロフィールが語られていた。
ハックルベリーは自分の気持のままに行動した。天気がよければ、どこかの家の玄関の階段で眠り、雨が降れば、大きな空樽のなかで眠った。学校へも教会へも行く必要がなかったし、誰のいうこともきく必要がなかった。釣りでも泳ぎでも、好きなとき、好きなところへ行くことができ、好きなだけ、そこにいることができた。喧嘩をしてはいけないと叱るものもいなかったし、いくらでも夜ふかしができた。春になると、誰よりも先に跣足になり、秋になると、誰よりも遅くまで靴をはかなかった。顔を洗ったり、きれいな服を着なくてもよかったし、どんなひどい言葉だって言いたいほうだいだった。要するに、人生を価値あるものにするために役立つすべてのことができるのだ。
まさしく、ハックルベリーは「浪漫的な宿なし小僧」であったわけだ。社会学的な、定住と漂泊とのあわいに生きるひき裂かれた存在といった、異人=ストレンジャーの定義を知ったあとには、ハックルベリーの肖像は異人以外の何かではありえない。残念ながら、わたしの『異人論序説』というはじめての著作では、ハックルベリーを取りあげることはなかった。子どものころに親しく交わったハックのことを、すっかり忘れていたからである。わたしが住んでいた平屋の都営住宅にも、学校に行かず、毎日うろうろ彷徨っている少年がいた。子だくさんの家で、わるい噂が絶えなかった。空き巣騒ぎがあると、その少年が決まって疑われた。もはや、北多摩の都営住宅のハックは、ほかの子どもたちから愛されもせず、いっしょに遊ぶこともなかったのだ。「学校って、何をするの?」と寂しそうに呟いた、少年の顔は忘れられない。
トムやハックたちが海賊遊びに興じる、特別な場所があった。ミシシッピ川の中洲であったか、人里離れた無人島があり、鬱蒼とした陰気な森が広がっていた。そこで、少年たちは「自由で野生的な饗宴」を催しながら、もう二度と文明社会へは戻りたくない、と語らいあった。文化と野生とが交錯する、人の住まぬ中洲の島と原始林など、境界を論じるための格好のフィールドであった。
鬱蒼とした森ではなかったが、武蔵野の雑木林のなかは、トムやハックが遊んだ中洲の島みたいなものだった。探検ごっこの舞台になった。カブトやクワガタの捕れる蜜の出る樹があり、スズメバチと戦わねば獲物にたどり着けなかった。子どもの掌二つ分くらいの大きさの貝を見つけた。ヒロシくんと相談して、石で叩いて半分に割って、それぞれに大事に持ち帰った。すこし意地のわるい上級生が、それは化石っていうんだ、と自慢そうに教えてくれた。半分だけの貝の化石は、狭い庭の片隅に捨て置かれ、いつしか雨に打たれながら存在そのものを忘却されていった。あるいは、冬眠から覚めたばかりの大きなガマガエルを、十数人の子どもらで石打ちの刑にした。あの異形の醜い生け贄をゾワゾワする高揚感のなかで殺した、まさしくサクリファイスの場面は、いまだに生々しく覚えている。はるか後年になって、ルネ・ジラールの『暴力と聖なるもの』を読んだときに、「全員一致の暴力」という言葉に出会って、あのガマガエル殺しの興奮を思いだし、妙に納得した。また、雑木林の奥へ、奥へと分け入ってゆくあやしい人影を追跡すると、エロ本が草葉の蔭に棄てられてあった。何日かして、また訪れたときには、すでに跡形もなく消えていた。
都営住宅からは遠く離れた、校区のはずれにある浅間山もまた、もうひとつの無人島であった。浅間山の手前には、米軍ハウスがあって、金髪の青い眼をした男の子たちが釘をかざして攻撃してきた。それを何とかかわさねば、オタマジャクシの捕れる水溜まりにはたどり着けなかった。いつだって、親には内緒で向かう浅間山は禁忌を漂わせていた。中学生になったばかりのころには、浅間山にある洞窟の探検に出かけた。それはまさしく、『トム・ソーヤーの冒険』の後追いのような、禁じられた冒険であった。鍾乳洞の垂れ下がる、迷路のような洞窟ではなかったが、戦時中に掘られた防空壕は危険だからと、近づくのを禁じられていた。石片に刻まれた文様のような小粒の貝の化石を見つけた。戦時中には、そこは弾薬庫として使われていたらしい。それを知ったのは、武蔵野を調べはじめた最近のことだ。
幼いわたしは、トムとハックを導者にして、ささやかな冒険の日々を送っていたのだ、と思う。断言してもいい。まわりの大人たちは誰ひとりとして、そんなことには気づいていなかったはずだ。「幻想性の時代」を生きている子どもたちはきっと、不可視の身体をしている。そうして、見えない男の子は本を携えて、冒険の旅に出る。どこに向かうとも知らずに。