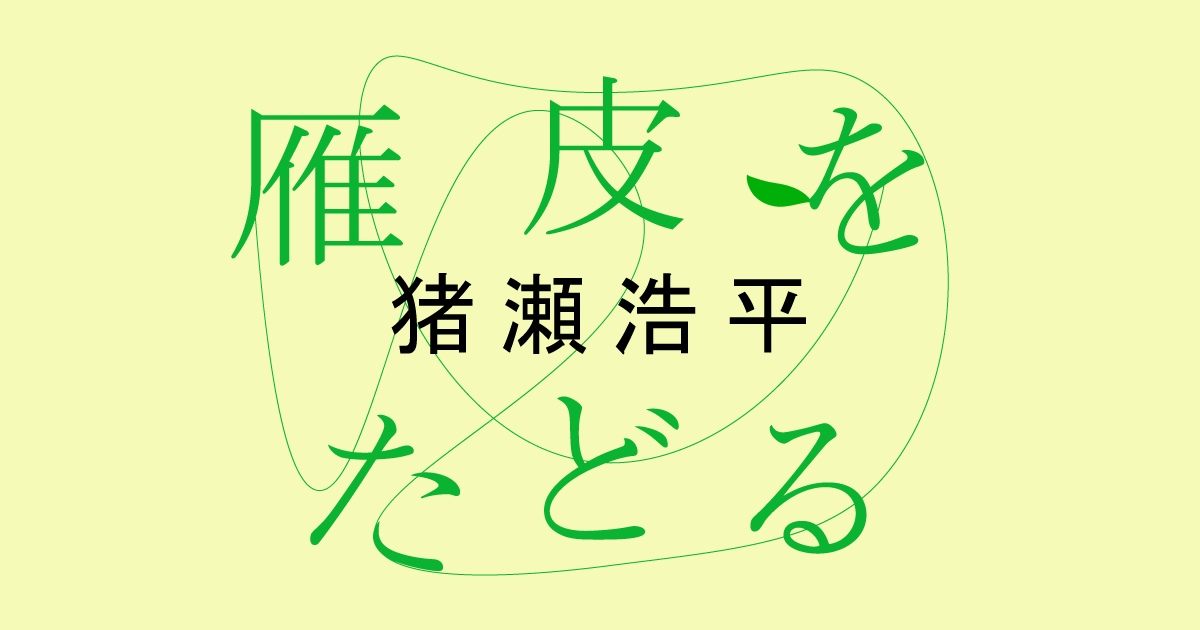雁皮は、人間がおもうようには育たない。わたしが話をきいた、ある製紙会社の社長は、群生しているところに雁皮を採りに行ったら、全部なくなっていたことがあると語った。長年、雁皮の採集をし、雁皮を仕入れ、原料にする紙を機械で抄いてきたその人にとっても、雁皮の生態は謎に含まれている部分が多くある。2024年2月に山口の森を歩いたたっさんの驚きも、その雁皮やそれが育つ生態の謎の中にある。
雁皮の栽培には、多くの人が挑戦してきた。高知出身の吉井源太が1877(明治10)年の第1回内国勧業博覧会に雁皮を主原料にした薄様大判紙を出品すると、複写用の原板となるコッピー紙として適していると評価され、欧米にむけた輸出品として大きく期待されるようになった。雁皮を使った紙は謄写版原紙や、タイプライター用紙としても高く評価されていく。[1] 紙幣原料としても注目されるなかで、伊豆の楳原寛重は1882年に「雁皮栽培録」を出版し、自らが試みた人工栽培記録を報告した。1889(明治22)年に福岡の江夏利兵衛が書いた『雁皮栽培法』では、西洋諸国において強靭平滑で彩色鮮明である和紙の評価が高く、大きな需要があるが、その最も有望な原料である供給が少なく、大蔵省印刷局資用すら不十分であるとし、生糸や茶を越える国益をもたらすものとして生産力を高めるための栽培法を紹介した。
しかし、雁皮の栽培は普及はしなかった。熊野における雁皮採集の状況と、伊豆における楳原の栽培記録を紹介した日下部兼道、北西敬二は「三椏はその栽培容易なるに反し、雁皮は生長遅く、その生育地が一部地方に限られて居るため、その繊維良質なるにもかかわらず、一般に栽培せらるるに至らず」と述べている(日下部・北西1940:69)。1998年の時点でも、当時金沢美術工芸大学教授の柳橋眞は雁皮の栽培について、「昔から何人も挑戦しながら失敗している(柳橋1998:3)」と書いている。
ハマダさんの祈り
ハマダさんは「この土におうてくれるかな」とつぶやきながら、雁皮を定植した。そして苗の周りの土を、祈るように手で固めた。
四万十町で桜の開花が始まった2025年3月14日に植えられた雁皮は、ハマダさんが2024年の4月に育苗用のポットに一粒一粒植え、育ててきたものだ。発芽してしっかりと根づくまで、雨で種が流されないように屋根を付け、暑さ対策のために、遮光性の黒い幕もつけた。発芽した直後にカタツムリやナメクジが覆いかぶさって新芽を食べてしまうことがあったため、ポットが直接地面に触れないよう苗場の床をコンクリートで固め、その周りにカタツムリやナメクジ除けの薬をまいた。
それでも2024年の猛暑は厳しかったこともあり、一年育てた苗の生育は必ずしも良くはなかった。2024年4月に2000粒の種をまいたが、育ったのは200本だけだった。その200本もポットの中に根っこがはっていないものが多くあり、10本に1本は定植作業に耐えられず、折れてしまう。折れてしまった苗をよけつつ、1メートルの間隔で、唐鍬とつるはしで穴を掘り、雁皮を植える。土の中に空洞を生まないよう、握りこぶしで固め、さらに足で踏み固める。植えた場所がわかるよう、一本一本棒を刺した。3月の上旬に植えた50本は、あらかじめ日光を通さない防草シートが敷かれたところに植えてあり、一本一本に目印のピンクのリボンが付けられていた。こちらは育ちがよかったものが選ばれていて、生育も悪くない。
山の尾根に位置するその圃場は、もともとスギやヒノキの人工林だった。十数年前に伐採されたあとに雑木が生え、育った。それを雁皮の圃場にするため、朝霧森林倶楽部の人びとがチェンソーで伐採し、ユンボを使えるメンバーが根っこを掘り出してならした。日当たりはよい。表面を掘り進めると赤土が見える。圃場にはシカの足跡があった。
朝霧森林倶楽部のメンバーはハマダさんを筆頭に片腕として活躍するカジタさん、フカヤさん、十和地区から活動に参加するマツシタさん、そしてわたしと学生のタバタ君、わたしの職場の先輩であるカツマタさん。ひょんな縁で知り合った、地元住民のジュン君を加えた8人の男たちで140本の雁皮、その傍らにコルクを2本植えた。作業が終わって、山を下りる。急峻な作業路は、四駆の軽トラでないと登り降りできない。この土に合っても、シカの食害に合わないか、順調に育ち、太ってくれるのか不安とともに祈りながら、軽トラはヒノキ林のあいだにつくられた林道を下っていく。
***
2025年3月の出来事を書き記しながら、わたしはアメリカのジャーナリスト、マイケル・ポーランが『欲望の植物誌』に書いた、次の言葉を思う。
およそ一万年前、世界は次なる植物多様性の開花に立ち会った。私たちが自己中心的に呼ぶところの「農業の発明」だ。被子植物のあるグループが、自分たちの基本的戦略――「動物に働かせよう作戦」に磨きをかけ、ある動物を利用しはじめたのだ。その動物は、地球上を自由に動きまわれるだけでなく、考えること、また複雑な考えをやりとりすることができるように進化していた。これらの植物は、驚くほど賢い作戦を打ちだした――私たちが、彼らのために動いたり考えたりするように仕向けたのだ。今や植物のなかから、人間に広大な森を切り開かせ、自分たちのためにより広い場所をつくらせるイネの仲間が現れた(麦やトウモロコシもその一員だ)。その美しさの前に、どの文化も釘づけになってしまう花が現れた。あまりに魅力的で、役に立ち、おいしいため、人間をしてタネを蒔かせ、輸送させ、激賞させ、それについて本さえ書かせるような植物がでてきた。この本も、そんな風にして書かれたもののひとつだ。(ポーラン2003:21)
被子植物は、華やかな花や大きな種子をつけ、それに様々な細工をほどこすことでほかの生物に自分の繁殖の手伝いをさせる。ハマダさんたちは雁皮の種を採取し、その苗をつくり、4ヘクタール余りの雑木林を切り開いて定植する。それは、雁皮を育てて和紙の原料としたいという願いであり、それによってこの地域の若い世代の人たちに継承可能な生業をつくりだしたいという願いである。そこに雁皮をつかって紙をつくる人たちの、国産の雁皮を求める願いが重なる。
とともに、ポーランは、人間が自然に対する自らの役割を過大評価する傾向があることも指摘する。人間が、自分自身のためだとおもって行う自然への介入や、自然にかかわる禁忌の設定、特定の植物の賛美は、自然の側からすれば単なる偶然であり、天候の変化のような要素と変わりがない。
ただ、事態はポーランが書いたことよりもさらに進んでいるようにも思われる。2001年にこの本において、天候の変化が人間の諸活動の蓄積によってもたらされるという人新世的な状況は意識されていない。大変な夏の暑さや、少ない雨、あるいは時に起こる猛烈な雨といった気候の変動のなかに、ハマダさんたちの雁皮栽培の試みもあり、祈りもある。
朝霧森林倶楽部
朝霧森林俱楽部は、高知県の四万十町で森林保全活動を行う、ボランティア団体である。
2006年に大正町、十和村と合併し四万十町となる窪川町に、原子力発電所が計画されたのが1980年。町内には原発を誘致しようとする人びとと、原発を建設すべきでないという人たちがそれぞれ立ち上がり、激しい衝突と静かなすれ違いを生んだ。長い時間が経った。原発を推進する町長のリコール、住民投票条例の制定、県漁連の反対決議、チェルノブイリ原発事故とその影響、そして電力需要の低迷といった出来事が国内外、地域内外に起き、やがて原発を推進する町長が辞任した。原発問題が争点にならない形の町長選挙が行われ、新しい町長が生まれた後、1988年に町会議員が推進派も反対派も超えて、全会一致で原発論議の終結宣言を議会で決議した。結論を得るまで、多数決に頼らず、うんざりするような長い時間もみ合い続け、最終的に全会一致で原発論議を終結させるまでの過程を、かつてわたしは「原発計画をもみ消した」と書いた[2]。町内の人びとの様々な想いがぶつかり、すれ違い、こすれあった経験は美しいものでも、勝利でも敗北でもない。それでももみ合い続けることは、この土地に生きていた人たちが原発騒動以前から対話を続けてきたことの証である。
原発反対運動のリーダーの一人が、シマオカさんだ。シマオカさんは農家であり、酪農家であり、林家でもある。生命を育てる一次産業と、生命を傷つける放射性物質を排出する原発は相いれないと、計画が持ち上がる頃から反対運動の中心に立ち、長年、町議会議員も務めた。1992年に原発騒動が終息し、町議会がだんだんとおちついていくなかで、シマオカさんは健全な森づくりと保全活動、四万十川の清流と水流の回復のために、人工林の除間伐を議員仲間に呼びかけた。
集まったのはシマオカさんを含めて3人。原発反対派はシマオカさんだけで、あとの2人は推進派だった。そのうちの1人は原発を推進する団体の事務局長だった。3人の議員を中心にはじまった活動を足掛かりに、2003年に朝霧森林倶楽部が結成された。ボランティアとして参加した人びとの中には町外からの移住者も多く、林業の経験がない人が大半だった。この年は、高知県が全国にさきがけて導入した森林環境税の始まった年で、森林環境税を原資とする補助金からチェンソーなどの道具を購入した[3]。朝霧森林倶楽部は、2014年度に林野庁の「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」をもとに、四万十町内の森の間伐作業を始めた。2015年度にはNPO法人として認可された。
朝霧森林倶楽部が、四万十町十和地区にある御成婚の森の整備を始めたのは2014年からのことだ。御成婚の森は、十和村が、当時の皇太子徳仁の結婚を祝って整備したものだ。やがて森は、合併に向かう村内の混乱のなかで管理が行き届かなくなり、荒れてしまう。四万十川を挟み、十和の道の駅に対面する位置にある御成婚の森を日々眺めていた住民たちの声を受け、御成婚の森の除間伐とサクラやモミジ、サルスベリ、ドウタンツツジなどの植樹が始まった。
2015年には、地元の中学生も参加し除伐・間伐作業を行った。そして2016年度には、十和地区住民、四万十町行政、朝霧森林倶楽部で「御成婚の森活用促進実行委員会」を結成し、御成婚の森管理育成授業を受託した。
光が入るようになったこの森に、雁皮が芽を出した。
注
[1]滋賀県の蒲生出身の堀井新治郎が、エジソンが発明したミメオグラフをヒントに1894年に鉄筆印刷による謄写版印刷を発明し、東京神田で謄写堂を開業した。堀井は雁皮紙にロウをひき、謄写版原紙とした。謄写版印刷は発売直後に起きた日清戦争において、陸軍の軍事通信用に採用された。謄写版印刷を体験した兵士が故郷に帰る流れで全国に普及し、やがて海外にも輸出されるようになった。タイプライターが主流になっていく欧米に対し、漢字やひらがな、カタカナ、ハングルなど多様な文字を持つ東アジア諸国に、鉄筆をつかって自由に描ける謄写版印刷は普及した。そうやって軍需から民需の転換が起きる中で、謄写版原紙の需要は拡大し、それに伴い雁皮の需要も拡大した。雁皮紙を使用した謄写版原紙は海外でも高く評価され、市場を拡大していく(田村・志村1985)。雁皮の需要の高まりのなかで、雁皮自生地の山野の景観がどのように変わっていったのかというのは、重要な論点になるだろう。近代化や国際市場への開放・進出、戦争や植民地経営といった事柄と雁皮は絡まりあい、それが雁皮自身が生きる景観を変え、資源化されることで雁皮は個体数を減らしていく。
[2] このことについては、拙著『むらと原発――窪川原発計画をもみ消した四万十の人びと』(農山漁村文化協会)を参照。
[3] 個人、法人ともに県民税の均等割に年額500円を上乗せして徴収される。令和7年度の活用事業費総額は2億44万円であり、野生動物の保護、森林環境学習、県民が行う森林保全活動などに活用される(『高知県森林環境税 令和7年度・活用事業のご案内』より)。
参考文献
楳原寛重 1940「雁皮栽培録」関編上掲書、85-93
楳原寛重 1940「続雁皮栽培録」関編上掲書、94-108
日下部兼道、北西敬二 1940「雁皮と其の人工栽培資料」関彪編『雁皮聚録』丸善株式会社、68-84
田村紀雄・志村章子編著 1985『ガリ版文化史:手づくりメディアの物語』新宿書房
ポーラン,P 2003『欲望の植物誌――人をあやつる4つの植物』西田佐知子訳、八坂書房
柳橋眞 1998「楮と漆の仲間」『季刊和紙』15:2-3